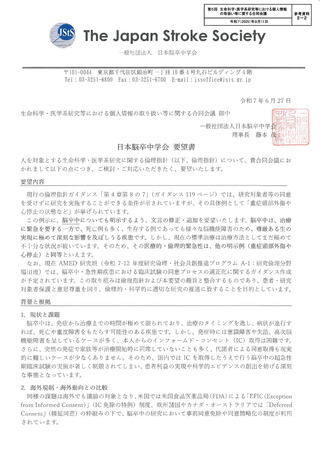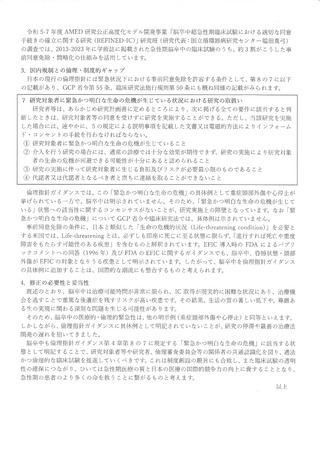よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2-2 : 日本脳卒中学会要望書 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63268.html |
| 出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第13回 9/11)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和 5-7 年度 AMED 研究公正高度化モデル開発事業「脳卒中超急性期臨床試験における適切な同意
手続きの確立に関する研究 (REFINED-IC)] 研究班 (研究代表 : 国立循環器病研究センター福田真弓)
の調査では、2013-2023 年に学術誌に操載された急性期脳卒中の臨床試験のうち、約 3 割がこうした事
前同意免除・簡略化の仕組みを活用しています。
3. 国内規制との倫理・制度的ギャップ
日本の現行の備理指針には累急状況下における事前同意免除を許容する条件として、第8 の7 に以下
の記載があり、GCP 省令第 55 条、了臨床研究法施行規則第 50 条にも概ね同様の記載がみられます。
7 研究対象者に繋急かつ明白な生命の危機が生じている状況における研究の取扱い
研究者等は、あらかじめ研究計画書に定めるところにより、次に掲げる全ての要件に該当すると判
断したときは、研究対象者等の同意を受けずに研究を実施することができる。ただし、当該研究を実施
した場合には、 速やかに、5 の規定による説明事項を記載した文書又は電磁的方法によりインフォーム
ド・コンセントの手続を行わなければならない。
① 研究対象者に緊急かつ明白な生命の危機が生じていること
② 介入を行う研究の場合には、通常の診療では十分な効果が期待できず、研究の実施により研究対象
者の生命の危機が回避できる可能性が十分にあると認められること
③ 研究の実施に伴って研究対象者に生じる負担及びリスクが必要最小限のものであること
④ 代諾者又は代諾者となるべき者と起ちに連絡を取ることができないこと
倫理指針ガイダンスでは、この |羅急かつ明白な生命の危機」 の具体例として重症頭部外傷や心停止が
挙げられている一方で、脳卒中は明示されていません。そのため、「緊急かつ明白な生命の危機が生じて
いる]| 状態への該当性に関するコンセンサスがないことが、 研究実施上の障壁となっています。なお「緊
急かつ明白な生命の危機」 について GCP 省令や臨床研究法では、具体例は示されていません。
事前同意免除の条件に、日本と類似した「生命の危機的状況 (Life-threatening condition) 」 を必要と
する米国では、Life-threatening とは、必ずしゃ即座に死亡に至る状態に限らちらず、 |進行すれば死亡や重度
障害をもたらす可能性のある疾患] を含むゃのと解釈されています。EFIC 導入時の FDA によるパブリ
ックコメントへの回答 (1996 年) 及び FDA の EFIC に関するガイダンスでやゃも、脳卒中、皆膝状態・頭部
外傷が EFIC の対象となりうる疾患として明示されています。したがって、脳卒中を倫理指針ガイダンス
の具体例に追加することは、国際的な潮流にも整合するものと考えられます。
4. 修正の必要性と妥当性
既述のとおり、脳卒中は治療可能時間が非常に限られ、IC 取得が現実的に困難な状況にあり、治療機
会を逃すことで重篤な後遺赴を残すサリスクが高い疾患です。その結果、生活の質の著しい低下や、 尊厳あ
る生の実現に関わる深刻な問題を生じる可能性があります。
そのため、 脳卒中の医療的・倫理的緊急性は、他の明示例 (重症頭部外傷や心停止) と同等といえます。
しかしながら、倫理指針がガイダンスに具体例として明記されていないことが、研究の停滞や最善の治療法
開発の遅れを招いてきました。
脳卒中ゃ倫理指針ガイダンス第 4 章第8 の 7 に規定する「緊急かつ明白な生命の危機」 に該当する状
態として明記することで、 研究対象者等や研究者、 倫理審査委員会等の関係者の共通認識化を図 9 、 適法
かつ備理的な臨床試験を推進していくべきです。 これは制度創設の趣旨にゃも合致し、また臨床試験の透明
性の確保につながり、ひいては急性期医療の質と日本の医療の国際的競争力の向上に資することとなり、
急性期の患者のより多くの命を救うことに繋がるものと考えます。
以上
手続きの確立に関する研究 (REFINED-IC)] 研究班 (研究代表 : 国立循環器病研究センター福田真弓)
の調査では、2013-2023 年に学術誌に操載された急性期脳卒中の臨床試験のうち、約 3 割がこうした事
前同意免除・簡略化の仕組みを活用しています。
3. 国内規制との倫理・制度的ギャップ
日本の現行の備理指針には累急状況下における事前同意免除を許容する条件として、第8 の7 に以下
の記載があり、GCP 省令第 55 条、了臨床研究法施行規則第 50 条にも概ね同様の記載がみられます。
7 研究対象者に繋急かつ明白な生命の危機が生じている状況における研究の取扱い
研究者等は、あらかじめ研究計画書に定めるところにより、次に掲げる全ての要件に該当すると判
断したときは、研究対象者等の同意を受けずに研究を実施することができる。ただし、当該研究を実施
した場合には、 速やかに、5 の規定による説明事項を記載した文書又は電磁的方法によりインフォーム
ド・コンセントの手続を行わなければならない。
① 研究対象者に緊急かつ明白な生命の危機が生じていること
② 介入を行う研究の場合には、通常の診療では十分な効果が期待できず、研究の実施により研究対象
者の生命の危機が回避できる可能性が十分にあると認められること
③ 研究の実施に伴って研究対象者に生じる負担及びリスクが必要最小限のものであること
④ 代諾者又は代諾者となるべき者と起ちに連絡を取ることができないこと
倫理指針ガイダンスでは、この |羅急かつ明白な生命の危機」 の具体例として重症頭部外傷や心停止が
挙げられている一方で、脳卒中は明示されていません。そのため、「緊急かつ明白な生命の危機が生じて
いる]| 状態への該当性に関するコンセンサスがないことが、 研究実施上の障壁となっています。なお「緊
急かつ明白な生命の危機」 について GCP 省令や臨床研究法では、具体例は示されていません。
事前同意免除の条件に、日本と類似した「生命の危機的状況 (Life-threatening condition) 」 を必要と
する米国では、Life-threatening とは、必ずしゃ即座に死亡に至る状態に限らちらず、 |進行すれば死亡や重度
障害をもたらす可能性のある疾患] を含むゃのと解釈されています。EFIC 導入時の FDA によるパブリ
ックコメントへの回答 (1996 年) 及び FDA の EFIC に関するガイダンスでやゃも、脳卒中、皆膝状態・頭部
外傷が EFIC の対象となりうる疾患として明示されています。したがって、脳卒中を倫理指針ガイダンス
の具体例に追加することは、国際的な潮流にも整合するものと考えられます。
4. 修正の必要性と妥当性
既述のとおり、脳卒中は治療可能時間が非常に限られ、IC 取得が現実的に困難な状況にあり、治療機
会を逃すことで重篤な後遺赴を残すサリスクが高い疾患です。その結果、生活の質の著しい低下や、 尊厳あ
る生の実現に関わる深刻な問題を生じる可能性があります。
そのため、 脳卒中の医療的・倫理的緊急性は、他の明示例 (重症頭部外傷や心停止) と同等といえます。
しかしながら、倫理指針がガイダンスに具体例として明記されていないことが、研究の停滞や最善の治療法
開発の遅れを招いてきました。
脳卒中ゃ倫理指針ガイダンス第 4 章第8 の 7 に規定する「緊急かつ明白な生命の危機」 に該当する状
態として明記することで、 研究対象者等や研究者、 倫理審査委員会等の関係者の共通認識化を図 9 、 適法
かつ備理的な臨床試験を推進していくべきです。 これは制度創設の趣旨にゃも合致し、また臨床試験の透明
性の確保につながり、ひいては急性期医療の質と日本の医療の国際的競争力の向上に資することとなり、
急性期の患者のより多くの命を救うことに繋がるものと考えます。
以上