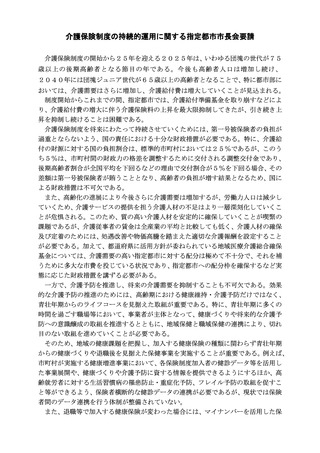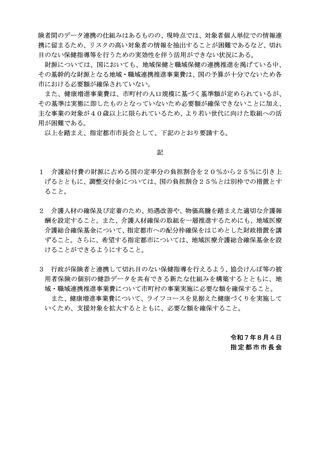よむ、つかう、まなぶ。
介護保険制度の持続的運用に関する指定都市市長会要請 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.siteitosi.jp/conference/activity/2025/r07_08_04_04.html |
| 出典情報 | 介護保険制度の持続的運用に関する指定都市市長会要請(8/4)《指定都市市長会》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
介護保険制度の持続的運用に関する指定都市市長会要請
介護保険制度の開始から25年を迎える2025年は、いわゆる団塊の世代が75
歳以上の後期高齢者となる節目の年である。今後も高齢者人口は増加し続け、
2040年には団塊ジュニア世代が65歳以上の高齢者となることで、特に都市部に
おいては、介護需要はさらに増加し、介護給付費は増大していくことが見込まれる。
制度開始からこれまでの間、指定都市では、介護給付準備基金を取り崩すなどによ
り、介護給付費の増大に伴う介護保険料の上昇を最大限抑制してきたが、引き続き上
昇を抑制し続けることは困難である。
介護保険制度を将来にわたって持続させていくためには、第一号被保険者の負担が
過重とならないよう、国の責任における十分な財政措置が必要である。特に、介護給
付の財源に対する国の負担割合は、標準的市町村においては25%であるが、このう
ち5%は、市町村間の財政力の格差を調整するために交付される調整交付金であり、
後期高齢者割合が全国平均を下回るなどの理由で交付割合が5%を下回る場合、その
差額は第一号被保険者が賄うこととなり、高齢者の負担が増す結果となるため、国に
よる財政措置は不可欠である。
また、高齢化の進展により今後さらに介護需要は増加するが、労働力人口は減少し
ていくため、介護サービスの提供を担う介護人材の不足はより一層深刻化していくこ
とが危惧される。このため、質の高い介護人材を安定的に確保していくことが喫緊の
課題であるが、介護従事者の賃金は全産業の平均と比較しても低く、介護人材の確保
及び定着のためには、処遇改善や物価高騰を踏まえた適切な介護報酬を設定すること
が必要である。加えて、都道府県に活用方針が委ねられている地域医療介護総合確保
基金については、介護需要の高い指定都市に対する配分は極めて不十分で、それを補
うために多大な市費を投じている状況であり、指定都市への配分枠を確保するなど実
態に応じた財政措置を講ずる必要がある。
一方で、介護予防を推進し、将来の介護需要を抑制することも不可欠である。効果
的な介護予防の推進のためには、高齢期における健康維持・介護予防だけではなく、
青壮年期からのライフコースを見据えた取組が重要である。特に、青壮年期に多くの
時間を過ごす職場等において、事業者が主体となって、健康づくりや将来的な介護予
防への意識醸成の取組を推進するとともに、地域保健と職域保健の連携により、切れ
目のない取組を進めていくことが必要である。
そのため、地域の健康課題を把握し、加入する健康保険の種類に関わらず青壮年期
からの健康づくりや退職後を見据えた保健事業を実施することが重要である。例えば、
市町村が実施する健康増進事業において、各保険制度加入者の健診データ等を活用し
た事業展開や、健康づくりや介護予防に資する情報を提供できるようにするほか、高
齢就労者に対する生活習慣病の罹患防止・重症化予防、フレイル予防の取組を促すこ
と等ができるよう、保険者横断的な健診データの連携が必要であるが、現状では保険
者間のデータ連携を行う体制が整備されていない。
また、退職等で加入する健康保険が変わった場合には、マイナンバーを活用した保
介護保険制度の開始から25年を迎える2025年は、いわゆる団塊の世代が75
歳以上の後期高齢者となる節目の年である。今後も高齢者人口は増加し続け、
2040年には団塊ジュニア世代が65歳以上の高齢者となることで、特に都市部に
おいては、介護需要はさらに増加し、介護給付費は増大していくことが見込まれる。
制度開始からこれまでの間、指定都市では、介護給付準備基金を取り崩すなどによ
り、介護給付費の増大に伴う介護保険料の上昇を最大限抑制してきたが、引き続き上
昇を抑制し続けることは困難である。
介護保険制度を将来にわたって持続させていくためには、第一号被保険者の負担が
過重とならないよう、国の責任における十分な財政措置が必要である。特に、介護給
付の財源に対する国の負担割合は、標準的市町村においては25%であるが、このう
ち5%は、市町村間の財政力の格差を調整するために交付される調整交付金であり、
後期高齢者割合が全国平均を下回るなどの理由で交付割合が5%を下回る場合、その
差額は第一号被保険者が賄うこととなり、高齢者の負担が増す結果となるため、国に
よる財政措置は不可欠である。
また、高齢化の進展により今後さらに介護需要は増加するが、労働力人口は減少し
ていくため、介護サービスの提供を担う介護人材の不足はより一層深刻化していくこ
とが危惧される。このため、質の高い介護人材を安定的に確保していくことが喫緊の
課題であるが、介護従事者の賃金は全産業の平均と比較しても低く、介護人材の確保
及び定着のためには、処遇改善や物価高騰を踏まえた適切な介護報酬を設定すること
が必要である。加えて、都道府県に活用方針が委ねられている地域医療介護総合確保
基金については、介護需要の高い指定都市に対する配分は極めて不十分で、それを補
うために多大な市費を投じている状況であり、指定都市への配分枠を確保するなど実
態に応じた財政措置を講ずる必要がある。
一方で、介護予防を推進し、将来の介護需要を抑制することも不可欠である。効果
的な介護予防の推進のためには、高齢期における健康維持・介護予防だけではなく、
青壮年期からのライフコースを見据えた取組が重要である。特に、青壮年期に多くの
時間を過ごす職場等において、事業者が主体となって、健康づくりや将来的な介護予
防への意識醸成の取組を推進するとともに、地域保健と職域保健の連携により、切れ
目のない取組を進めていくことが必要である。
そのため、地域の健康課題を把握し、加入する健康保険の種類に関わらず青壮年期
からの健康づくりや退職後を見据えた保健事業を実施することが重要である。例えば、
市町村が実施する健康増進事業において、各保険制度加入者の健診データ等を活用し
た事業展開や、健康づくりや介護予防に資する情報を提供できるようにするほか、高
齢就労者に対する生活習慣病の罹患防止・重症化予防、フレイル予防の取組を促すこ
と等ができるよう、保険者横断的な健診データの連携が必要であるが、現状では保険
者間のデータ連携を行う体制が整備されていない。
また、退職等で加入する健康保険が変わった場合には、マイナンバーを活用した保