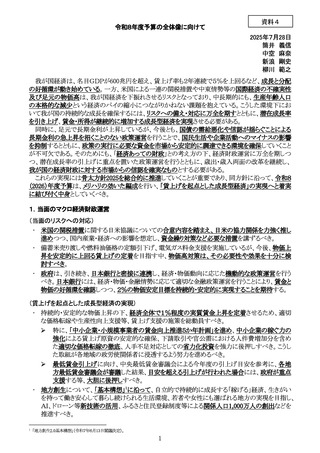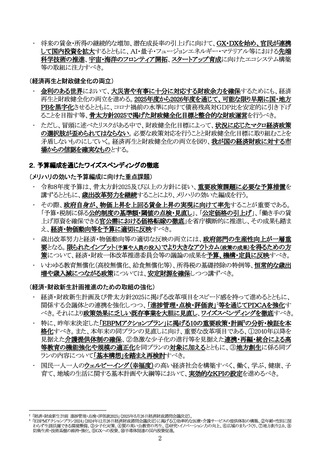よむ、つかう、まなぶ。
資料4 令和8年度予算の全体像に向けて(有識者議員提出資料) (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2025/0728agenda.html |
| 出典情報 | 経済財政諮問会議(第9回 7/28)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和8年度予算の全体像に向けて
資料4
2025年7月28日
筒井 義信
中空 麻奈
新浪 剛史
柳川 範之
我が国経済は、名目GDPが600兆円を超え、賃上げ率も2年連続で5%を上回るなど、成長と分配
の好循環が動き始めている。一方、米国による一連の関税措置や中東情勢等の国際経済の不確実性
及び足元の物価高は、我が国経済を下振れさせるリスクとなっており、中長期的にも、生産年齢人口
の本格的な減少という経済のパイの縮小につながりかねない課題を抱えている。こうした環境下にお
いて我が国の持続的な成長を確保するには、リスクへの備え・対応に万全を期すとともに、潜在成長率
を引き上げ、賃金・所得が継続的に増加する成長型経済を実現させる必要がある。
同時に、足元で長期金利が上昇しているが、今後とも、国債の需給悪化や信認が揺らぐことによる
長期金利の急上昇を招くことのない政策運営を行うことで、国民生活や企業活動へのマイナスの影響
を抑制するとともに、政策の実行に必要な資金を市場から安定的に調達できる環境を確保していくこと
が不可欠である。そのためにも、「経済あっての財政」との考え方の下、経済財政運営に万全を期しつ
つ、潜在成長率の引上げに重点を置いた政策運営を行うとともに、歳出・歳入両面の改革を継続し、
我が国の経済財政に対する市場からの信認を確実なものとする必要がある。
これらの実現には骨太方針2025を総合的に推進していくことが重要であり、同方針に沿って、令和8
(2026)年度予算は、メリハリの効いた編成を行い、「賃上げを起点とした成長型経済」の実現へと着実
に結び付く中身としていくべき。
1.当面のマクロ経済財政運営
(当面のリスクへの対応)
米国の関税措置に関する日米協議についての合意内容を踏まえ、日米の協力関係を力強く推し
進めつつ、国内産業・経済への影響を想定し、資金繰り対策など必要な措置を講ずるべき。
備蓄米売り渡しや燃料油価格の定額引下げ、電気ガス料金支援を実施しているが、今後、物価上
昇を安定的に上回る賃上げの定着を目指す中、物価高対策は、その必要性や効果を十分に検
討すべき。
政府は、引き続き、日本銀行と密接に連携し、経済・物価動向に応じた機動的な政策運営を行う
べき。日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と
物価の好循環を確認しつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
(賃上げを起点とした成長型経済の実現)
持続的・安定的な物価上昇の下、経済全体で1%程度の実質賃金上昇を定着させるため、適切
な価格転嫁や生産性向上支援等、賃上げ支援の施策を総動員すべき。
特に、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画」を進め、中小企業の稼ぐ力の
強化による賃上げ原資の安定的な確保、下請取引や官公需における人件費増加分を含め
た適切な価格転嫁の徹底、人手不足対応としての省力化投資を強力に後押しすべき。こうし
た取組が各地域の政労使関係者に浸透するよう努力を進めるべき。
最低賃金引上げに向け、中央最低賃金審議会による今年度の引上げ目安を参考に、各地
方最低賃金審議会が審議した結果、目安を超える引上げが行われた場合には、政府が重点
支援する等、大胆に後押しすべき。
地方創生について、「基本構想」1に沿って、自立的で持続的に成長する「稼げる」経済、生きがい
を持って働き安心して暮らし続けられる生活環境、若者や女性にも選ばれる地方の実現を目指し、
AI、ドローン等新技術の活用、ふるさと住民登録制度等による関係人口1,000万人の創出などを
推進すべき。
1
「地方創生2.0基本構想」(令和7年6月13日閣議決定)。
1
資料4
2025年7月28日
筒井 義信
中空 麻奈
新浪 剛史
柳川 範之
我が国経済は、名目GDPが600兆円を超え、賃上げ率も2年連続で5%を上回るなど、成長と分配
の好循環が動き始めている。一方、米国による一連の関税措置や中東情勢等の国際経済の不確実性
及び足元の物価高は、我が国経済を下振れさせるリスクとなっており、中長期的にも、生産年齢人口
の本格的な減少という経済のパイの縮小につながりかねない課題を抱えている。こうした環境下にお
いて我が国の持続的な成長を確保するには、リスクへの備え・対応に万全を期すとともに、潜在成長率
を引き上げ、賃金・所得が継続的に増加する成長型経済を実現させる必要がある。
同時に、足元で長期金利が上昇しているが、今後とも、国債の需給悪化や信認が揺らぐことによる
長期金利の急上昇を招くことのない政策運営を行うことで、国民生活や企業活動へのマイナスの影響
を抑制するとともに、政策の実行に必要な資金を市場から安定的に調達できる環境を確保していくこと
が不可欠である。そのためにも、「経済あっての財政」との考え方の下、経済財政運営に万全を期しつ
つ、潜在成長率の引上げに重点を置いた政策運営を行うとともに、歳出・歳入両面の改革を継続し、
我が国の経済財政に対する市場からの信認を確実なものとする必要がある。
これらの実現には骨太方針2025を総合的に推進していくことが重要であり、同方針に沿って、令和8
(2026)年度予算は、メリハリの効いた編成を行い、「賃上げを起点とした成長型経済」の実現へと着実
に結び付く中身としていくべき。
1.当面のマクロ経済財政運営
(当面のリスクへの対応)
米国の関税措置に関する日米協議についての合意内容を踏まえ、日米の協力関係を力強く推し
進めつつ、国内産業・経済への影響を想定し、資金繰り対策など必要な措置を講ずるべき。
備蓄米売り渡しや燃料油価格の定額引下げ、電気ガス料金支援を実施しているが、今後、物価上
昇を安定的に上回る賃上げの定着を目指す中、物価高対策は、その必要性や効果を十分に検
討すべき。
政府は、引き続き、日本銀行と密接に連携し、経済・物価動向に応じた機動的な政策運営を行う
べき。日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と
物価の好循環を確認しつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
(賃上げを起点とした成長型経済の実現)
持続的・安定的な物価上昇の下、経済全体で1%程度の実質賃金上昇を定着させるため、適切
な価格転嫁や生産性向上支援等、賃上げ支援の施策を総動員すべき。
特に、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画」を進め、中小企業の稼ぐ力の
強化による賃上げ原資の安定的な確保、下請取引や官公需における人件費増加分を含め
た適切な価格転嫁の徹底、人手不足対応としての省力化投資を強力に後押しすべき。こうし
た取組が各地域の政労使関係者に浸透するよう努力を進めるべき。
最低賃金引上げに向け、中央最低賃金審議会による今年度の引上げ目安を参考に、各地
方最低賃金審議会が審議した結果、目安を超える引上げが行われた場合には、政府が重点
支援する等、大胆に後押しすべき。
地方創生について、「基本構想」1に沿って、自立的で持続的に成長する「稼げる」経済、生きがい
を持って働き安心して暮らし続けられる生活環境、若者や女性にも選ばれる地方の実現を目指し、
AI、ドローン等新技術の活用、ふるさと住民登録制度等による関係人口1,000万人の創出などを
推進すべき。
1
「地方創生2.0基本構想」(令和7年6月13日閣議決定)。
1