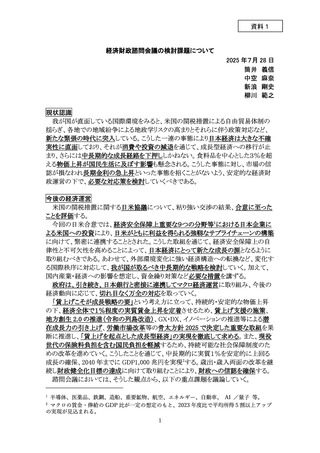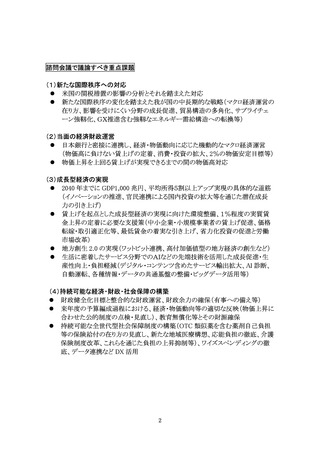よむ、つかう、まなぶ。
資料1 経済財政諮問会議の検討課題について(有識者議員提出資料) (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2025/0728agenda.html |
| 出典情報 | 経済財政諮問会議(第9回 7/28)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
資料1
経済財政諮問会議の検討課題について
2025 年7月 28 日
筒井 義信
中空 麻奈
新浪 剛史
柳川 範之
現状認識
我が国が直面している国際環境をみると、米国の関税措置による自由貿易体制の
揺らぎ、各地での地域紛争による地政学リスクの高まりとそれらに伴う政策対応など、
新たな緊張の時代に突入している。こうした一連の事態により日本経済は大きな不確
実性に直面しており、それが消費や投資の減退を通じて、成長型経済への移行が止
まり、さらには中長期的な成長経路を下押ししかねない。食料品を中心とした3%を超
える物価上昇が国民生活に及ぼす影響も懸念される。こうした事態に対し、市場の信
認が損なわれ長期金利の急上昇といった事態を招くことがないよう、安定的な経済財
政運営の下で、必要な対応策を検討していくべきである。
今後の経済運営
米国の関税措置に関する日米協議について、粘り強い交渉の結果、合意に至った
ことを評価する。
今回の日米合意では、経済安全保障上重要な9つの分野等1における日本企業に
よる米国への投資により、日米がともに利益を得られる強靱なサプライチェーンの構築
に向けて、緊密に連携することとされた。こうした取組を通じて、経済安全保障上の自
律性と不可欠性を高めることによって、日本経済にとって新たな成長の源となるように
取り組むべきである。あわせて、外部環境変化に強い経済構造への転換など、変化す
る国際秩序に対応して、我が国が取るべき中長期的な戦略を検討していく。加えて、
国内産業・経済への影響を想定し、資金繰り対策など必要な措置を講ずる。
政府は、引き続き、日本銀行と密接に連携してマクロ経済運営に取り組み、今後の
経済動向に応じて、切れ目なく万全の対応を取っていく。
「賃上げこそが成長戦略の要」という考え方に立って、持続的・安定的な物価上昇
の下、経済全体で1%程度の実質賃金上昇を定着させるため、賃上げ支援の施策、
地方創生 2.0 の推進(令和の列島改造)、GX・DX、イノベーションの推進等による潜
在成長力の引き上げ、労働市場改革等の骨太方針 2025 で決定した重要な取組を果
断に推進し、「賃上げを起点とした成長型経済」の実現を徹底して求める。また、現役
世代の保険料負担を含む国民負担を軽減するため、持続可能な社会保障制度のた
めの改革を進めていく。こうしたことを通じて、中長期的に実質1%を安定的に上回る
成長の確保、2040 年までに GDP1,000 兆円を実現2する。歳出・歳入両面の改革を継
続し財政健全化目標の達成に向けて取り組むことにより、財政への信認を確保する。
諮問会議においては、そうした観点から、以下の重点課題を議論していく。
半導体、医薬品、鉄鋼、造船、重要鉱物、航空、エネルギー、⾃動⾞、 AI /量⼦ 等。
マクロの賃⾦・俸給の GDP ⽐が⼀定の想定のもと、2023 年度⽐で平均所得5割以上アップ
の実現が⾒込まれる。
1
2
1
経済財政諮問会議の検討課題について
2025 年7月 28 日
筒井 義信
中空 麻奈
新浪 剛史
柳川 範之
現状認識
我が国が直面している国際環境をみると、米国の関税措置による自由貿易体制の
揺らぎ、各地での地域紛争による地政学リスクの高まりとそれらに伴う政策対応など、
新たな緊張の時代に突入している。こうした一連の事態により日本経済は大きな不確
実性に直面しており、それが消費や投資の減退を通じて、成長型経済への移行が止
まり、さらには中長期的な成長経路を下押ししかねない。食料品を中心とした3%を超
える物価上昇が国民生活に及ぼす影響も懸念される。こうした事態に対し、市場の信
認が損なわれ長期金利の急上昇といった事態を招くことがないよう、安定的な経済財
政運営の下で、必要な対応策を検討していくべきである。
今後の経済運営
米国の関税措置に関する日米協議について、粘り強い交渉の結果、合意に至った
ことを評価する。
今回の日米合意では、経済安全保障上重要な9つの分野等1における日本企業に
よる米国への投資により、日米がともに利益を得られる強靱なサプライチェーンの構築
に向けて、緊密に連携することとされた。こうした取組を通じて、経済安全保障上の自
律性と不可欠性を高めることによって、日本経済にとって新たな成長の源となるように
取り組むべきである。あわせて、外部環境変化に強い経済構造への転換など、変化す
る国際秩序に対応して、我が国が取るべき中長期的な戦略を検討していく。加えて、
国内産業・経済への影響を想定し、資金繰り対策など必要な措置を講ずる。
政府は、引き続き、日本銀行と密接に連携してマクロ経済運営に取り組み、今後の
経済動向に応じて、切れ目なく万全の対応を取っていく。
「賃上げこそが成長戦略の要」という考え方に立って、持続的・安定的な物価上昇
の下、経済全体で1%程度の実質賃金上昇を定着させるため、賃上げ支援の施策、
地方創生 2.0 の推進(令和の列島改造)、GX・DX、イノベーションの推進等による潜
在成長力の引き上げ、労働市場改革等の骨太方針 2025 で決定した重要な取組を果
断に推進し、「賃上げを起点とした成長型経済」の実現を徹底して求める。また、現役
世代の保険料負担を含む国民負担を軽減するため、持続可能な社会保障制度のた
めの改革を進めていく。こうしたことを通じて、中長期的に実質1%を安定的に上回る
成長の確保、2040 年までに GDP1,000 兆円を実現2する。歳出・歳入両面の改革を継
続し財政健全化目標の達成に向けて取り組むことにより、財政への信認を確保する。
諮問会議においては、そうした観点から、以下の重点課題を議論していく。
半導体、医薬品、鉄鋼、造船、重要鉱物、航空、エネルギー、⾃動⾞、 AI /量⼦ 等。
マクロの賃⾦・俸給の GDP ⽐が⼀定の想定のもと、2023 年度⽐で平均所得5割以上アップ
の実現が⾒込まれる。
1
2
1