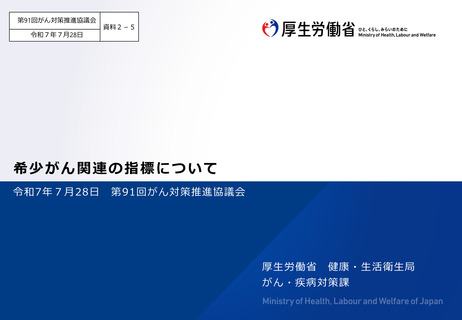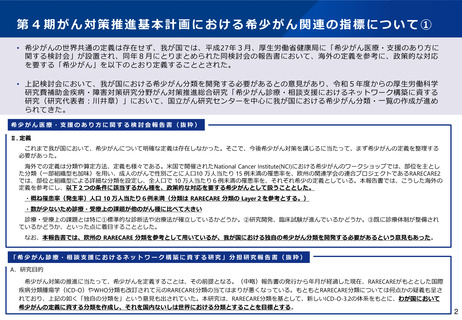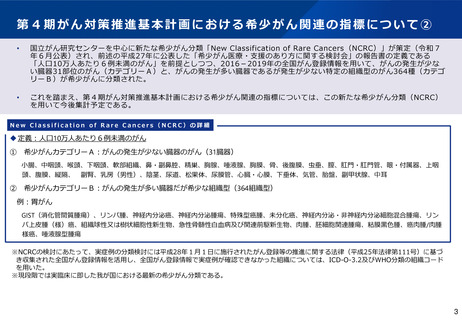よむ、つかう、まなぶ。
資料2-5 希少がん関連の指標について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60047.html |
| 出典情報 | がん対策推進協議会(第91回 7/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第4期がん対策推進基本計画における希少がん関連の指標について①
• 希少がんの世界共通の定義は存在せず、我が国では、平成27年3月、厚生労働省健康局に「希少がん医療・支援のあり方に
関する検討会」が設置され、同年8月にとりまとめられた同検討会の報告書において、海外の定義を参考に、政策的な対応
を要する「希少がん」を以下のとおり定義することとされた。
• 上記検討会において、我が国における希少がん分類を開発する必要があるとの意見があり、令和5年度からの厚生労働科学
研究費補助金疾病・障害対策研究分野がん対策推進総合研究「希少がん診療・相談支援におけるネットワーク構築に資する
研究(研究代表者:川井章)」において、国立がん研究センターを中心に我が国における希少がん分類・一覧の作成が進め
られてきた。
希少がん医療・支援のあり方に関する検討会報告書(抜粋)
Ⅱ. 定義
これまで我が国において、希少がんについて明確な定義は存在しなかった。そこで、今後希少がん対策を講じるに当たって、まず希少がんの定義を整理する
必要があった。
海外での定義は分類や算定方法、定義も様々である。米国で開催されたNational Cancer Institute(NCI)における希少がんのワークショップでは、部位を主とし
た分類(一部組織型も加味)を用い、成人のがんで性別ごとに人口10 万人当たり 15 例未満の罹患率を、欧州の関連学会の連合プロジェクトであるRARECARE2
では、部位と組織型による詳細な分類を設定し、全人口で 10 万人当たり6例未満の罹患率を、それぞれ希少の定義としている。本報告書では、こうした海外の
定義を参考にし、以下2つの条件に該当するがん種を、政策的な対応を要する希少がんとして扱うこととした。
・概ね罹患率(発生率)人口 10 万人当たり6例未満(分類は RARECARE 分類の Layer2を参考とする。)
・数が少ないため診療・受療上の課題が他のがん種に比べて大きい
診療・受療上の課題とは特に①標準的な診断法や治療法が確立しているかどうか。②研究開発、臨床試験が進んでいるかどうか。③既に診療体制が整備され
ているかどうか、といった点に着目することとした。
なお、本報告書では、欧州の RARECARE 分類を参考として用いているが、我が国における独自の希少がん分類を開発する必要があるという意見もあった。
「希少がん診療・相談支援におけるネットワーク構築に資する研究」分担研究報告書(抜粋)
A.研究目的
希少がん対策の推進に当たって、希少がんを定義することは、その前提となる。(中略)報告書の発行から年月が経過した現在、RARECAREがもととした国際
疾病分類腫瘍学(ICD-O)やWHO分類も改訂されて元のRARECARE分類の当てはまりが悪くなっている。もともとRARECARE分類については何点かの疑義も呈さ
れており、上記の如く「独自の分類を」という意見も出されていた。本研究は、RARECARE分類を基として、新しいICD-O-3.2の体系をもとに、わが国において
希少がんの定義に資する分類を作成し、それを国内ないしは世界における分類とすることを目標とする。
2
• 希少がんの世界共通の定義は存在せず、我が国では、平成27年3月、厚生労働省健康局に「希少がん医療・支援のあり方に
関する検討会」が設置され、同年8月にとりまとめられた同検討会の報告書において、海外の定義を参考に、政策的な対応
を要する「希少がん」を以下のとおり定義することとされた。
• 上記検討会において、我が国における希少がん分類を開発する必要があるとの意見があり、令和5年度からの厚生労働科学
研究費補助金疾病・障害対策研究分野がん対策推進総合研究「希少がん診療・相談支援におけるネットワーク構築に資する
研究(研究代表者:川井章)」において、国立がん研究センターを中心に我が国における希少がん分類・一覧の作成が進め
られてきた。
希少がん医療・支援のあり方に関する検討会報告書(抜粋)
Ⅱ. 定義
これまで我が国において、希少がんについて明確な定義は存在しなかった。そこで、今後希少がん対策を講じるに当たって、まず希少がんの定義を整理する
必要があった。
海外での定義は分類や算定方法、定義も様々である。米国で開催されたNational Cancer Institute(NCI)における希少がんのワークショップでは、部位を主とし
た分類(一部組織型も加味)を用い、成人のがんで性別ごとに人口10 万人当たり 15 例未満の罹患率を、欧州の関連学会の連合プロジェクトであるRARECARE2
では、部位と組織型による詳細な分類を設定し、全人口で 10 万人当たり6例未満の罹患率を、それぞれ希少の定義としている。本報告書では、こうした海外の
定義を参考にし、以下2つの条件に該当するがん種を、政策的な対応を要する希少がんとして扱うこととした。
・概ね罹患率(発生率)人口 10 万人当たり6例未満(分類は RARECARE 分類の Layer2を参考とする。)
・数が少ないため診療・受療上の課題が他のがん種に比べて大きい
診療・受療上の課題とは特に①標準的な診断法や治療法が確立しているかどうか。②研究開発、臨床試験が進んでいるかどうか。③既に診療体制が整備され
ているかどうか、といった点に着目することとした。
なお、本報告書では、欧州の RARECARE 分類を参考として用いているが、我が国における独自の希少がん分類を開発する必要があるという意見もあった。
「希少がん診療・相談支援におけるネットワーク構築に資する研究」分担研究報告書(抜粋)
A.研究目的
希少がん対策の推進に当たって、希少がんを定義することは、その前提となる。(中略)報告書の発行から年月が経過した現在、RARECAREがもととした国際
疾病分類腫瘍学(ICD-O)やWHO分類も改訂されて元のRARECARE分類の当てはまりが悪くなっている。もともとRARECARE分類については何点かの疑義も呈さ
れており、上記の如く「独自の分類を」という意見も出されていた。本研究は、RARECARE分類を基として、新しいICD-O-3.2の体系をもとに、わが国において
希少がんの定義に資する分類を作成し、それを国内ないしは世界における分類とすることを目標とする。
2