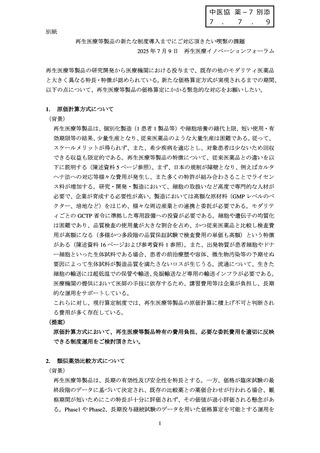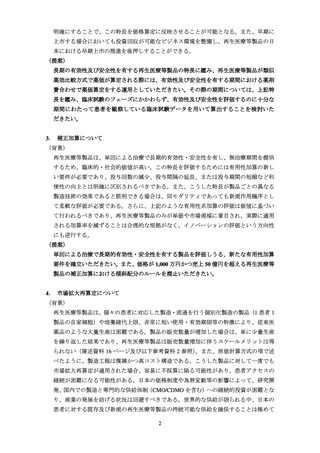よむ、つかう、まなぶ。
薬-7別添[308KB] (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59378.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第236回 7/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
中医 協 薬- 7 別 添
7 . 7 . 9
別紙
再生医療等製品の新たな制度導入までにご対応頂きたい喫緊の課題
2025 年 7 月 9 日 再生医療イノベーションフォーラム
再生医療等製品の研究開発から医療機関における投与まで、既存の他のモダリティ医薬品
と大きく異なる特長・特徴が認められている。新たな価格算定方式が実現されるまでの期間、
以下の点について、再生医療等製品の価格算定にかかる緊急的な対応をお願いしたい。
1. 原価計算方式について
(背景)
再生医療等製品は、個別化製造(1 患者 1 製品等)や細胞培養の継代上限、短い使用・有
効期限等の結果、少量生産となり、従来医薬品のような大量生産は困難である。従って、
スケールメリットが得られず、また、希少疾病を適応とし、対象患者は少ないため回収
できる収益も限定的である。再生医療等製品の特徴について、従来医薬品との違いを以
下に説明する(陳述資料 5 ページ参照)
。まず、日本の規制が障壁となり、例えばカルタ
ヘナ法への対応等様々な費用が発生し、また多くの特許が組み合わさることでライセン
ス料が増加する。研究・開発・製造において、細胞の取扱いなど高度で専門的な人材が
必要で、企業が育成する必要性が高い。製造においては高額な原材料(GMP レベルのベ
クター、培地など)をはじめ、様々な周辺産業との連携と委託が必要である。モダリテ
ィごとの GCTP 省令に準拠した専用設備への投資が必要である。細胞や遺伝子の均質化
は困難であり、品質検査の使用量が大きな割合を占め、かつ従来医薬品と比較し検査費
用が高額になる(多様かつ多段階の品質保証試験で検査費用の単価も高額)という特徴
がある(陳述資料 16 ページおよび参考資料 1 参照)
。また、出発物質が患者細胞やドナ
ー細胞といった生体試料である場合、患者の前治療歴や容体、微生物汚染等の予期せぬ
要因によって生体試料が製造品質を満たさないロスが生じうる。流通について、生きた
細胞の輸送には超低温での保管や輸送、免振輸送など専用の輸送インフラが必要である。
医療機関の提供において医師の手技に依存するため、講習費用等は企業が負担し、長期
的な運用をサポートしている。
これらに対し、現行算定制度では、再生医療等製品の原価計算に積上げ不可と判断され
る費用が多く存在している。
(提案)
原価計算方式において、再生医療等製品特有の費用負担、必要な委託費用を適切に反映
できる制度運用をご検討頂きたい。
2. 類似薬効比較方式について
(背景)
再生医療等製品は、長期の有効性及び安全性を特長とする。一方、価格が臨床試験の最
終段階のデータに基づいて決定され、既存の比較薬との薬価合わせが行われる場合、観
察期間が短いためにこの特長が十分に評価されず、その価値が過小評価される懸念があ
る。Phase1 や Phase2、長期投与継続試験のデータを用いた価格算定を可能とする運用を
1
7 . 7 . 9
別紙
再生医療等製品の新たな制度導入までにご対応頂きたい喫緊の課題
2025 年 7 月 9 日 再生医療イノベーションフォーラム
再生医療等製品の研究開発から医療機関における投与まで、既存の他のモダリティ医薬品
と大きく異なる特長・特徴が認められている。新たな価格算定方式が実現されるまでの期間、
以下の点について、再生医療等製品の価格算定にかかる緊急的な対応をお願いしたい。
1. 原価計算方式について
(背景)
再生医療等製品は、個別化製造(1 患者 1 製品等)や細胞培養の継代上限、短い使用・有
効期限等の結果、少量生産となり、従来医薬品のような大量生産は困難である。従って、
スケールメリットが得られず、また、希少疾病を適応とし、対象患者は少ないため回収
できる収益も限定的である。再生医療等製品の特徴について、従来医薬品との違いを以
下に説明する(陳述資料 5 ページ参照)
。まず、日本の規制が障壁となり、例えばカルタ
ヘナ法への対応等様々な費用が発生し、また多くの特許が組み合わさることでライセン
ス料が増加する。研究・開発・製造において、細胞の取扱いなど高度で専門的な人材が
必要で、企業が育成する必要性が高い。製造においては高額な原材料(GMP レベルのベ
クター、培地など)をはじめ、様々な周辺産業との連携と委託が必要である。モダリテ
ィごとの GCTP 省令に準拠した専用設備への投資が必要である。細胞や遺伝子の均質化
は困難であり、品質検査の使用量が大きな割合を占め、かつ従来医薬品と比較し検査費
用が高額になる(多様かつ多段階の品質保証試験で検査費用の単価も高額)という特徴
がある(陳述資料 16 ページおよび参考資料 1 参照)
。また、出発物質が患者細胞やドナ
ー細胞といった生体試料である場合、患者の前治療歴や容体、微生物汚染等の予期せぬ
要因によって生体試料が製造品質を満たさないロスが生じうる。流通について、生きた
細胞の輸送には超低温での保管や輸送、免振輸送など専用の輸送インフラが必要である。
医療機関の提供において医師の手技に依存するため、講習費用等は企業が負担し、長期
的な運用をサポートしている。
これらに対し、現行算定制度では、再生医療等製品の原価計算に積上げ不可と判断され
る費用が多く存在している。
(提案)
原価計算方式において、再生医療等製品特有の費用負担、必要な委託費用を適切に反映
できる制度運用をご検討頂きたい。
2. 類似薬効比較方式について
(背景)
再生医療等製品は、長期の有効性及び安全性を特長とする。一方、価格が臨床試験の最
終段階のデータに基づいて決定され、既存の比較薬との薬価合わせが行われる場合、観
察期間が短いためにこの特長が十分に評価されず、その価値が過小評価される懸念があ
る。Phase1 や Phase2、長期投与継続試験のデータを用いた価格算定を可能とする運用を
1