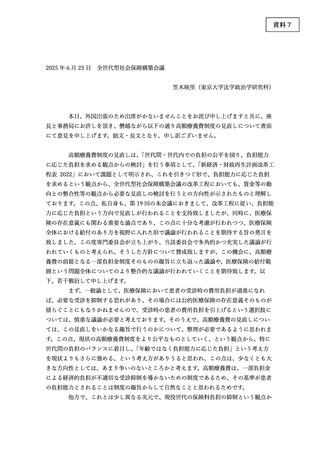よむ、つかう、まなぶ。
資料7 笠木構成員提出資料 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai21/gijisidai.html |
| 出典情報 | 全世代型社会保障構築会議(第21回 6/23)《内閣官房》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
らの給付範囲の見直しという文脈で、端的に高額療養費の引上げを検討するという考え方
がありえ、こうした考え方も改革工程や医療保険部会における議論には含まれていたもの
と思われます。私見では、このように保険料負担の抑制という観点から高額療養費の引き
上げを検討する場合には、この問題が医療保険における患者自己負担のあり方・医療保険
の給付範囲の問題の一端であることを十分に意識した上で、これらの問題を全体として視
野に入れつつ議論する必要があると考えます。具体的には、まず、言うまでも無いことで
すが、高額療養費の前提には 1 割〜3 割の受診時一部負担金が存在し、これらの一部負担
の仕組みにつき整合的な議論が行われる必要があると考えます。なお、一部負担金本体及
び高額療養費に共通する、年齢と所得の基準によって患者の費用負担の水準を異なるもの
とするという考え方は、日本の医療保険制度の特徴の一つといえると思いますが、外国の
立法例では、一部負担金本体について、例えば長期間にわたる治療の必要な疾病について
負担を軽減する制度や、薬剤の効果に応じて一部負担の水準を上限させる仕組みなどが散
見されるところ、日本ではそもそもあらゆる医療行為について原則 3 割、年齢と所得に応
じた例外、という、ある意味では形式的な制度になっており、年齢という基準の適切さを
含め、そもそも受診時の一部負担金がいかなる趣旨の制度なのか、今のような考え方のま
まで良いのか、高額療養費を考慮に入れつつ医療保険制度においていかなる実効給付率が
望ましいと考えるのか、等が問われても良いのではないかと考えます。
また、専門委員会の初回会合でも既に複数の委員が言及されている通り、そもそ
も、この問題は医療保険がどこまでの医療を給付範囲とできるのかという問題(新規薬
剤・医療機器の保険収載、さらには保険外併用療養費のあり方などを含む)のうちの一側
面とみるべきであり、保険料負担の抑制を目指した改革を行うにあたり、これらの様々な
論点のうち、
「医療を多く必要とする患者の一部負担金の上限」という論点を取出して、い
かなる負担のあり方が公平なのかを議論することが、問題の切り取り方・優先順位の付け
方として適切なのかも、本来は論点となり得るところではないかと思います。なお、この
問題については昨年末以降患者団体をはじめ直接に制度変更の影響を受ける当事者からの
強い不安と反発が示されたわけですが、現役世代の保険料負担の軽減という目的のために
なぜ受診時の患者自己負担の引上げという形での対応が必要なのか、という点について、
必ずしも多くの国民の理解を得られなかったという面もあるように感じております。勿
論、以上の論点はいずれも医療保険制度の根幹にかかわる難しい問題であり、これらを全
体として一挙に論じ、制度改革を行うことには現実味がなく、実際には個別の論点ごとに
段階を踏んで検討をせざるを得ないことも十分に理解できるところではございますが、こ
の問題が注目を集めているこの機会に、高額療養費の医療保険制度全体の中での位置付け
を十分に考慮した御議論を進めて頂きたいと期待しております次第です。
がありえ、こうした考え方も改革工程や医療保険部会における議論には含まれていたもの
と思われます。私見では、このように保険料負担の抑制という観点から高額療養費の引き
上げを検討する場合には、この問題が医療保険における患者自己負担のあり方・医療保険
の給付範囲の問題の一端であることを十分に意識した上で、これらの問題を全体として視
野に入れつつ議論する必要があると考えます。具体的には、まず、言うまでも無いことで
すが、高額療養費の前提には 1 割〜3 割の受診時一部負担金が存在し、これらの一部負担
の仕組みにつき整合的な議論が行われる必要があると考えます。なお、一部負担金本体及
び高額療養費に共通する、年齢と所得の基準によって患者の費用負担の水準を異なるもの
とするという考え方は、日本の医療保険制度の特徴の一つといえると思いますが、外国の
立法例では、一部負担金本体について、例えば長期間にわたる治療の必要な疾病について
負担を軽減する制度や、薬剤の効果に応じて一部負担の水準を上限させる仕組みなどが散
見されるところ、日本ではそもそもあらゆる医療行為について原則 3 割、年齢と所得に応
じた例外、という、ある意味では形式的な制度になっており、年齢という基準の適切さを
含め、そもそも受診時の一部負担金がいかなる趣旨の制度なのか、今のような考え方のま
まで良いのか、高額療養費を考慮に入れつつ医療保険制度においていかなる実効給付率が
望ましいと考えるのか、等が問われても良いのではないかと考えます。
また、専門委員会の初回会合でも既に複数の委員が言及されている通り、そもそ
も、この問題は医療保険がどこまでの医療を給付範囲とできるのかという問題(新規薬
剤・医療機器の保険収載、さらには保険外併用療養費のあり方などを含む)のうちの一側
面とみるべきであり、保険料負担の抑制を目指した改革を行うにあたり、これらの様々な
論点のうち、
「医療を多く必要とする患者の一部負担金の上限」という論点を取出して、い
かなる負担のあり方が公平なのかを議論することが、問題の切り取り方・優先順位の付け
方として適切なのかも、本来は論点となり得るところではないかと思います。なお、この
問題については昨年末以降患者団体をはじめ直接に制度変更の影響を受ける当事者からの
強い不安と反発が示されたわけですが、現役世代の保険料負担の軽減という目的のために
なぜ受診時の患者自己負担の引上げという形での対応が必要なのか、という点について、
必ずしも多くの国民の理解を得られなかったという面もあるように感じております。勿
論、以上の論点はいずれも医療保険制度の根幹にかかわる難しい問題であり、これらを全
体として一挙に論じ、制度改革を行うことには現実味がなく、実際には個別の論点ごとに
段階を踏んで検討をせざるを得ないことも十分に理解できるところではございますが、こ
の問題が注目を集めているこの機会に、高額療養費の医療保険制度全体の中での位置付け
を十分に考慮した御議論を進めて頂きたいと期待しております次第です。