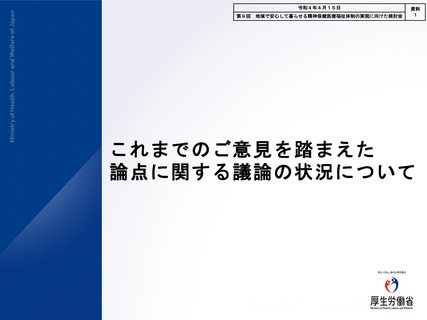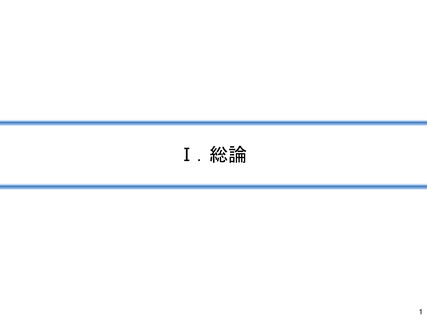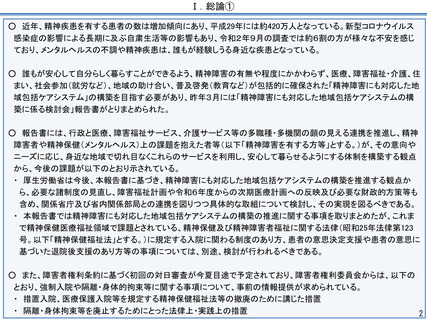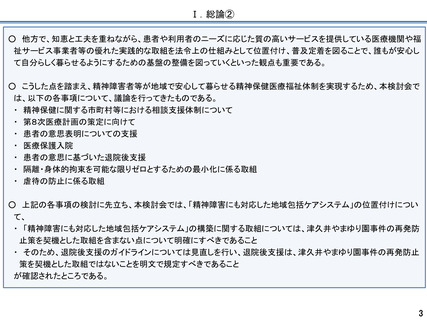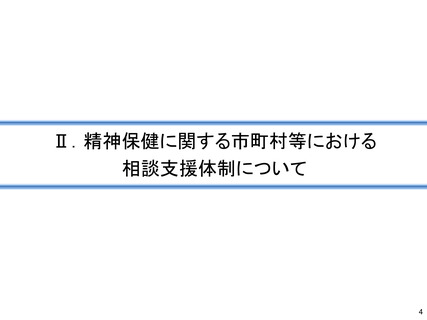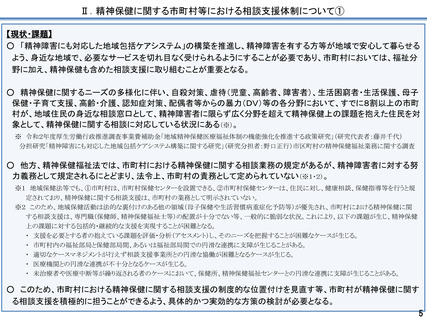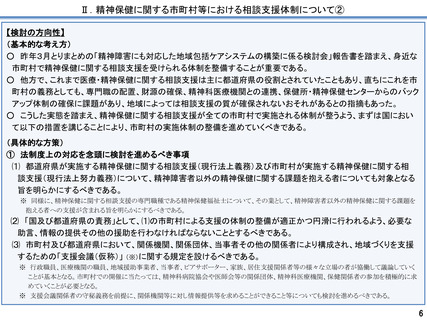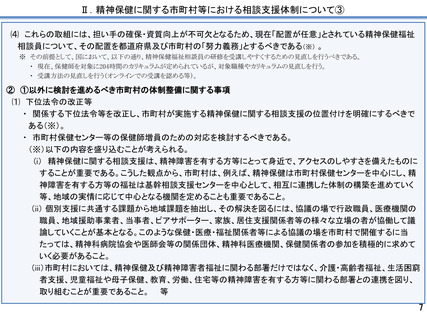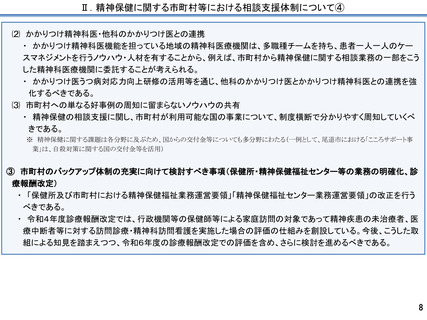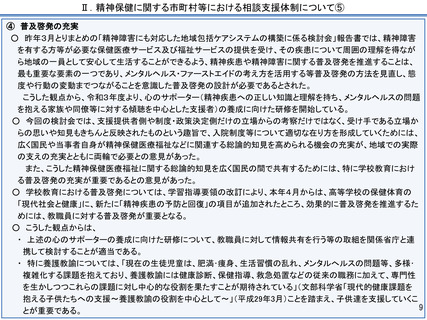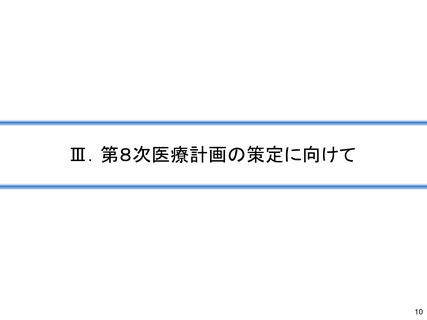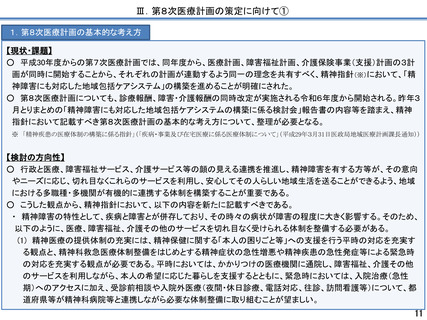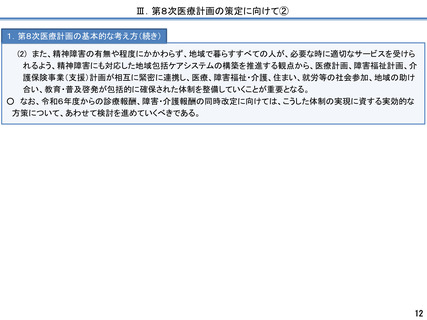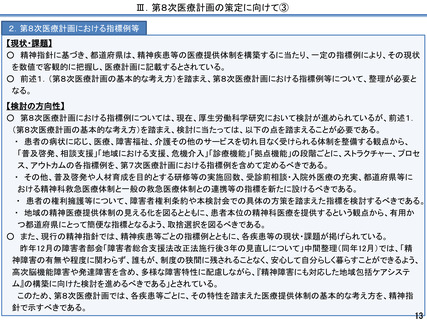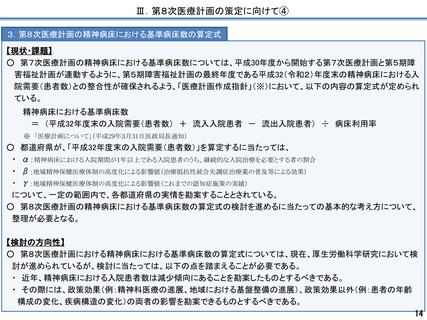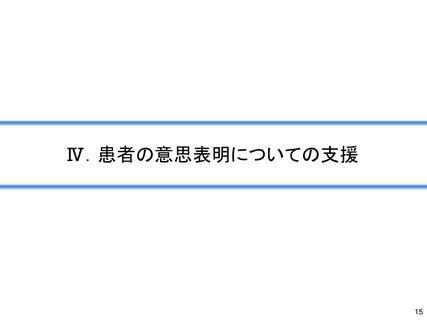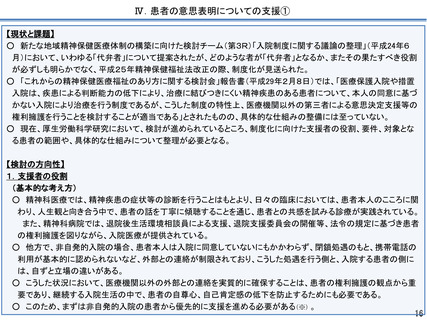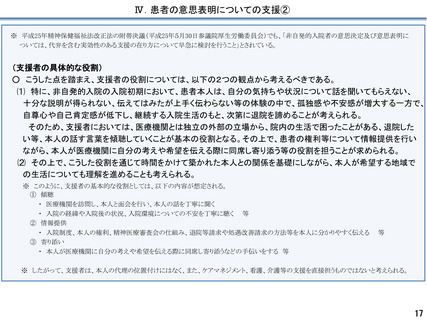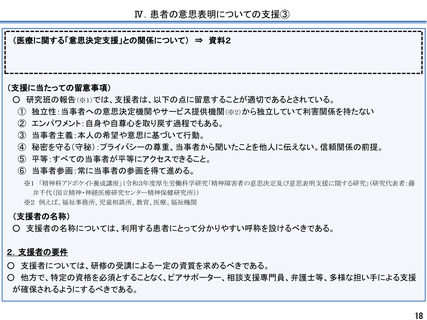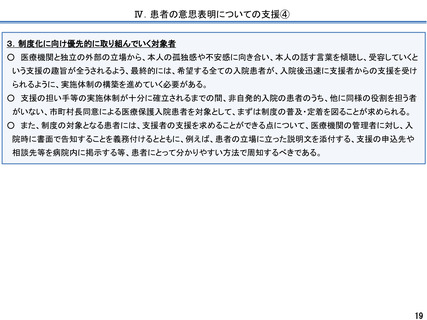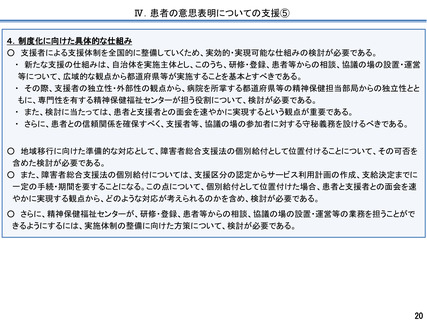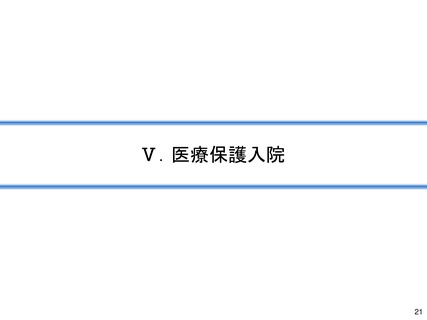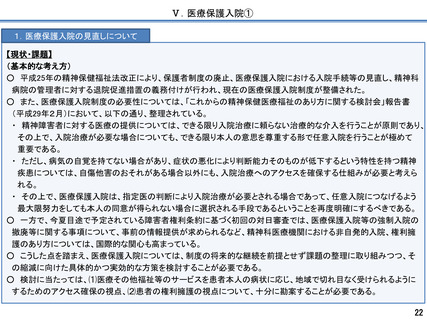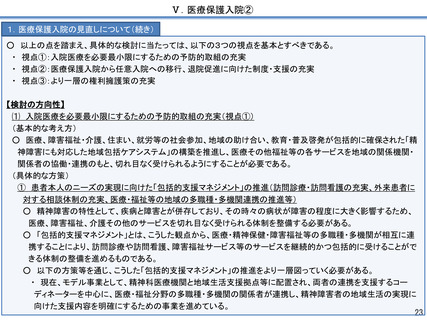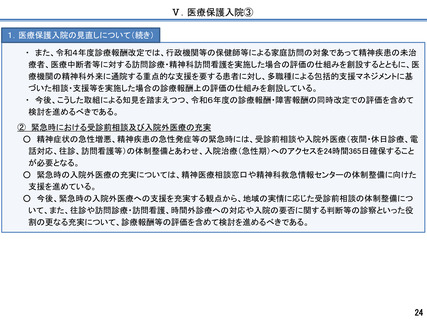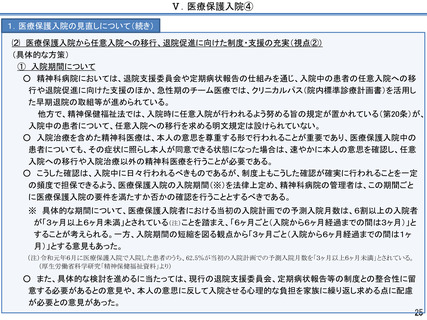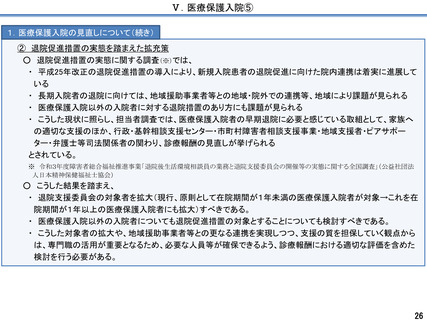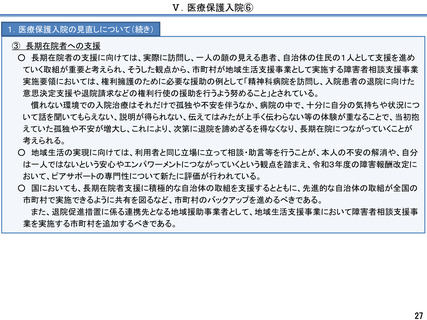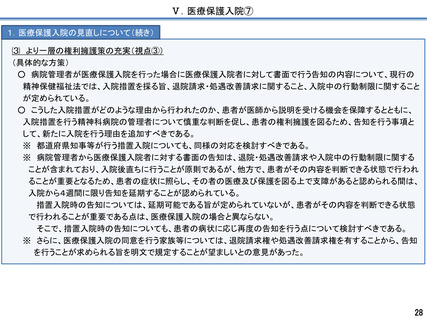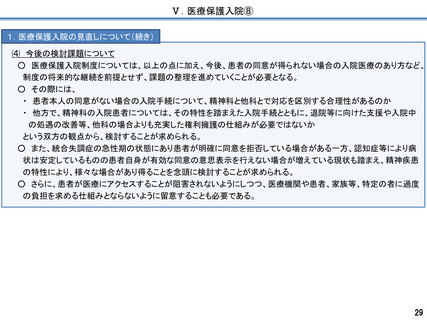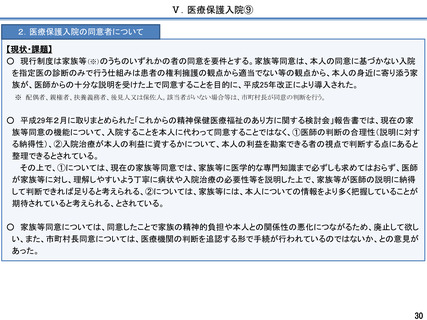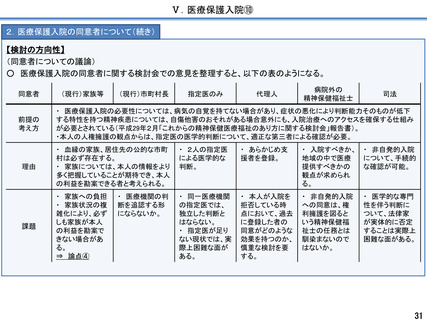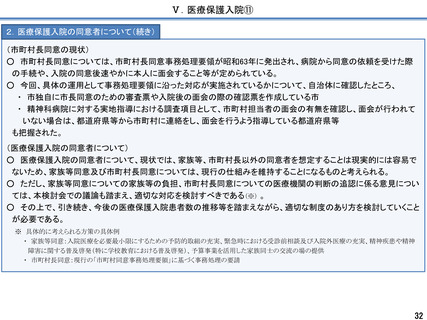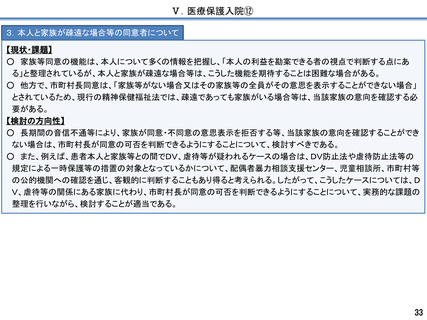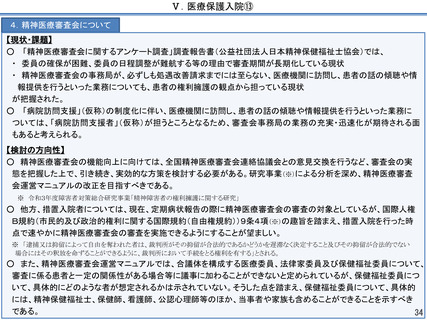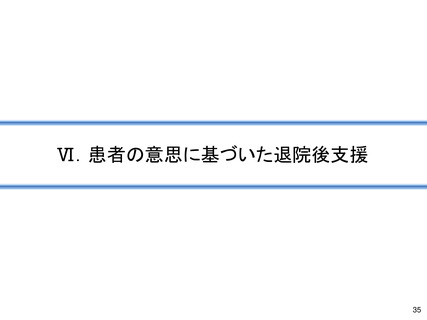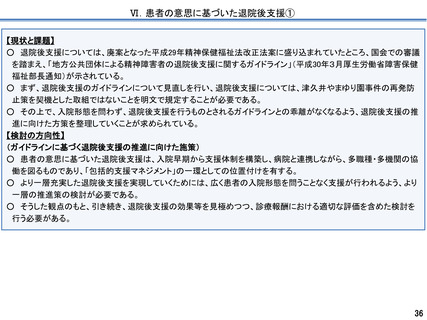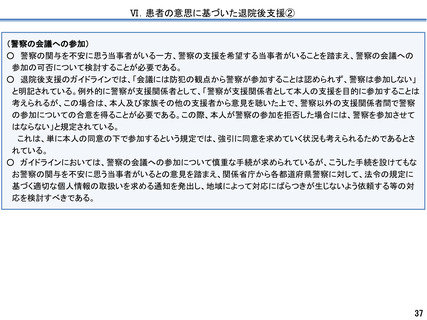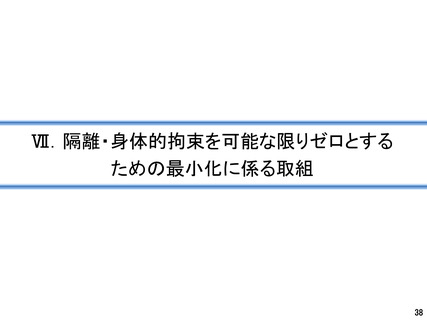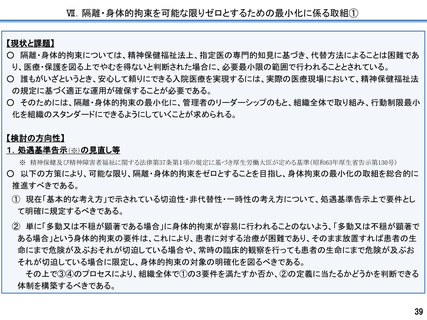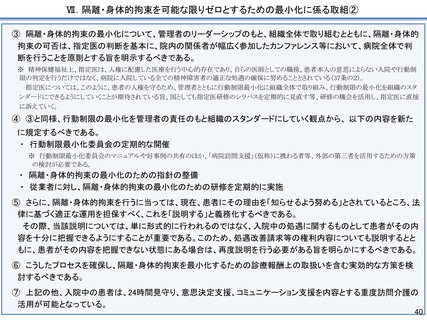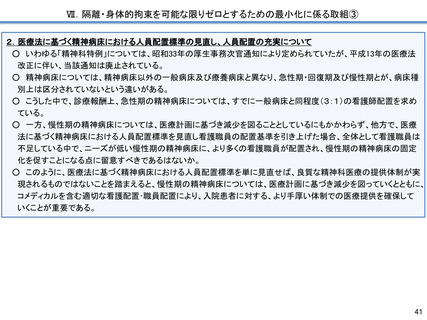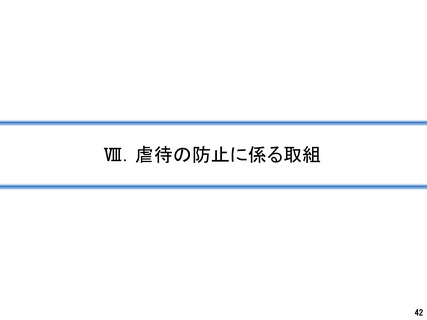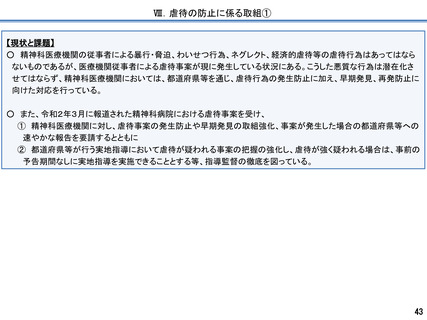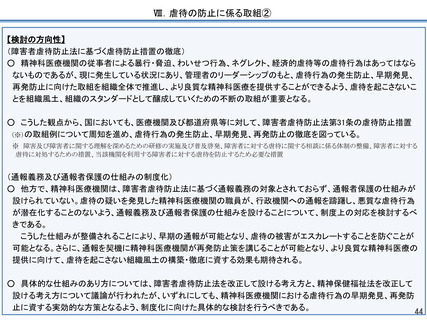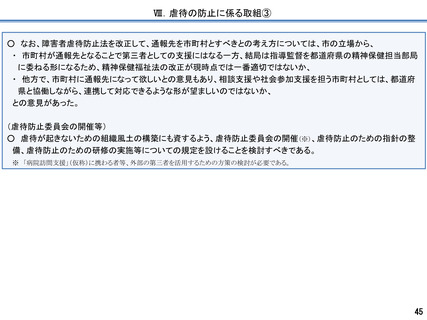よむ、つかう、まなぶ。
(資料1)これまでの御意見を踏まえた論点に関する議論について (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25241.html |
| 出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第9回 3/16)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅱ.精神保健に関する市町村等における相談支援体制について⑤
④ 普及啓発の充実
○ 昨年3月とりまとめの「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」報告書では、精神障害
を有する方等が必要な保健医療サービス及び福祉サービスの提供を受け、その疾患について周囲の理解を得なが
ら地域の一員として安心して生活することができるよう、精神疾患や精神障害に関する普及啓発を推進することは、
最も重要な要素の一つであり、メンタルヘルス・ファーストエイドの考え方を活用する等普及啓発の方法を見直し、態
度や行動の変動までつながることを意識した普及啓発の設計が必要であるとされた。
こうした観点から、令和3年度より、心のサポーター(精神疾患への正しい知識と理解を持ち、メンタルヘルスの問題
を抱える家族や同僚等に対する傾聴を中心とした支援者)の養成に向けた研修を開始している。
○ 今回の検討会では、支援提供者側や制度・政策決定側だけの立場からの考察だけではなく、受け手である立場か
らの思いや知見もきちんと反映されたものという趣旨で、入院制度等について適切な在り方を形成していくためには、
広く国民や当事者自身が精神保健医療福祉などに関連する総論的知見を高められる機会の充実が、地域での実際
の支えの充実とともに両輪で必要との意見があった。
また、こうした精神保健医療福祉に関する総論的知見を広く国民の間で共有するためには、特に学校教育におけ
る普及啓発の充実が重要であるとの意見があった。
○ 学校教育における普及啓発については、学習指導要領の改訂により、本年4月からは、高等学校の保健体育の
「現代社会と健康」に、新たに「精神疾患の予防と回復」の項目が追加されたところ、効果的に普及啓発を推進するた
めには、教職員に対する普及啓発が重要となる。
○ こうした観点からは、
・ 上述の心のサポーターの養成に向けた研修について、教職員に対して情報共有を行う等の取組を関係省庁と連
携して検討することが適当である。
・ 特に養護教諭については、「現在の生徒児童は、肥満・痩身、生活習慣の乱れ、メンタルへルスの問題等、多様・
複雑化する課題を抱えており、養護教諭には健康診断、保健指導、救急処置などの従来の職務に加えて、専門性
を生かしつつこれらの課題に対し中心的な役割を果たすことが期待されている」(文部科学省「現代的健康課題を
抱える子供たちへの支援~養護教諭の役割を中心として~」(平成29年3月)ことを踏まえ、子供達を支援していくこ
9
とが重要である。
④ 普及啓発の充実
○ 昨年3月とりまとめの「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」報告書では、精神障害
を有する方等が必要な保健医療サービス及び福祉サービスの提供を受け、その疾患について周囲の理解を得なが
ら地域の一員として安心して生活することができるよう、精神疾患や精神障害に関する普及啓発を推進することは、
最も重要な要素の一つであり、メンタルヘルス・ファーストエイドの考え方を活用する等普及啓発の方法を見直し、態
度や行動の変動までつながることを意識した普及啓発の設計が必要であるとされた。
こうした観点から、令和3年度より、心のサポーター(精神疾患への正しい知識と理解を持ち、メンタルヘルスの問題
を抱える家族や同僚等に対する傾聴を中心とした支援者)の養成に向けた研修を開始している。
○ 今回の検討会では、支援提供者側や制度・政策決定側だけの立場からの考察だけではなく、受け手である立場か
らの思いや知見もきちんと反映されたものという趣旨で、入院制度等について適切な在り方を形成していくためには、
広く国民や当事者自身が精神保健医療福祉などに関連する総論的知見を高められる機会の充実が、地域での実際
の支えの充実とともに両輪で必要との意見があった。
また、こうした精神保健医療福祉に関する総論的知見を広く国民の間で共有するためには、特に学校教育におけ
る普及啓発の充実が重要であるとの意見があった。
○ 学校教育における普及啓発については、学習指導要領の改訂により、本年4月からは、高等学校の保健体育の
「現代社会と健康」に、新たに「精神疾患の予防と回復」の項目が追加されたところ、効果的に普及啓発を推進するた
めには、教職員に対する普及啓発が重要となる。
○ こうした観点からは、
・ 上述の心のサポーターの養成に向けた研修について、教職員に対して情報共有を行う等の取組を関係省庁と連
携して検討することが適当である。
・ 特に養護教諭については、「現在の生徒児童は、肥満・痩身、生活習慣の乱れ、メンタルへルスの問題等、多様・
複雑化する課題を抱えており、養護教諭には健康診断、保健指導、救急処置などの従来の職務に加えて、専門性
を生かしつつこれらの課題に対し中心的な役割を果たすことが期待されている」(文部科学省「現代的健康課題を
抱える子供たちへの支援~養護教諭の役割を中心として~」(平成29年3月)ことを踏まえ、子供達を支援していくこ
9
とが重要である。