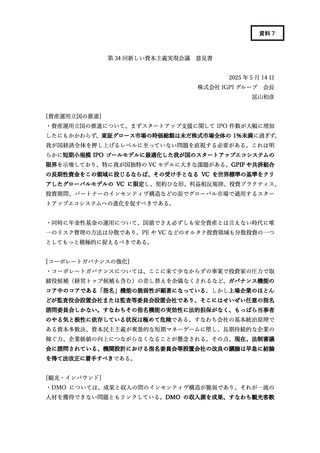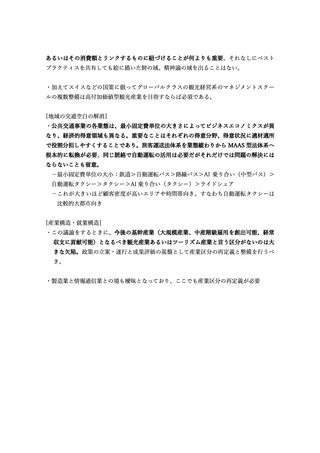よむ、つかう、まなぶ。
資料7冨山委員提出資料 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai34/gijisidai.html |
| 出典情報 | 新しい資本主義実現会議(第34回 5/14)《内閣官房》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
あるいはその消費額とリンクするものに紐づけることが何よりも重要。それなしにベスト
プラクティスを共有しても絵に描いた餅の域、精神論の域を出ることはない。
・加えてスイスなどの国策に倣ってグローバルクラスの観光経営系のマネジメントスクー
ルの複数整備は高付加価値型観光産業を目指すならば必須である。
[地域の交通空白の解消]
・公共交通事業の各業態は、最小固定費単位の大きさによってビジネスエコノミクスが異
なり、経済的得意領域も異なる。重要なことはそれぞれの得意分野、得意状況に適材適所
で役割分担しやすくすることであり。旅客運送法体系を業態縦わりから MAAS 型法体系へ
根本的に転換が必要。同じ脈絡で自動運転の活用は必要だがそれだけでは問題の解決には
ならないことも留意。
-最小固定費単位の大小:鉄道>自動運転バス>路線バス>AI 乗り合い(中型バス)>
自動運転タクシー>タクシー>AI 乗り合い(タクシー)>ライドシェア
-これが大きいほど顧客密度が高いエリアや時間帯向き。すなわち自動運転タクシーは
比較的大都市向き
[産業構造・就業構造]
・この議論をするときに、今後の基幹産業(大規模産業、中産階級雇用を創出可能、経常
収支に貢献可能)となるべき観光産業あるいはツーリズム産業と言う区分がないのは大
きな欠陥。政策の立案・遂行と成果評価の基盤として産業区分の再定義と整備を行うべ
き。
・製造業と情報通信業との境も曖昧となっており、ここでも産業区分の再定義が必要
プラクティスを共有しても絵に描いた餅の域、精神論の域を出ることはない。
・加えてスイスなどの国策に倣ってグローバルクラスの観光経営系のマネジメントスクー
ルの複数整備は高付加価値型観光産業を目指すならば必須である。
[地域の交通空白の解消]
・公共交通事業の各業態は、最小固定費単位の大きさによってビジネスエコノミクスが異
なり、経済的得意領域も異なる。重要なことはそれぞれの得意分野、得意状況に適材適所
で役割分担しやすくすることであり。旅客運送法体系を業態縦わりから MAAS 型法体系へ
根本的に転換が必要。同じ脈絡で自動運転の活用は必要だがそれだけでは問題の解決には
ならないことも留意。
-最小固定費単位の大小:鉄道>自動運転バス>路線バス>AI 乗り合い(中型バス)>
自動運転タクシー>タクシー>AI 乗り合い(タクシー)>ライドシェア
-これが大きいほど顧客密度が高いエリアや時間帯向き。すなわち自動運転タクシーは
比較的大都市向き
[産業構造・就業構造]
・この議論をするときに、今後の基幹産業(大規模産業、中産階級雇用を創出可能、経常
収支に貢献可能)となるべき観光産業あるいはツーリズム産業と言う区分がないのは大
きな欠陥。政策の立案・遂行と成果評価の基盤として産業区分の再定義と整備を行うべ
き。
・製造業と情報通信業との境も曖昧となっており、ここでも産業区分の再定義が必要