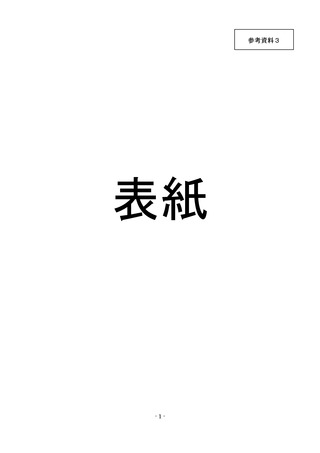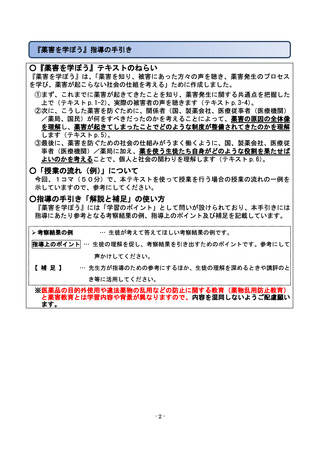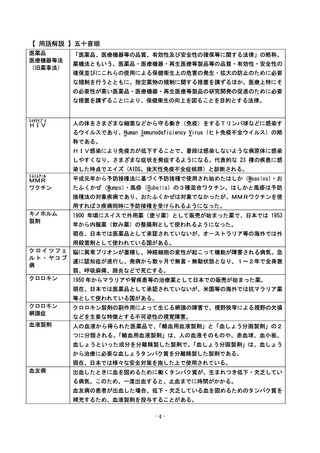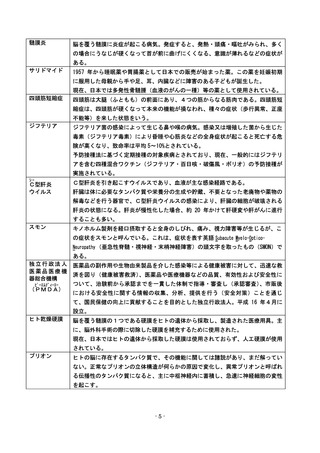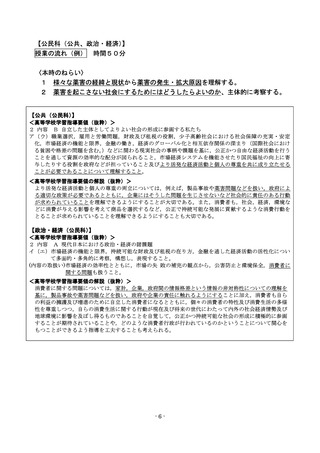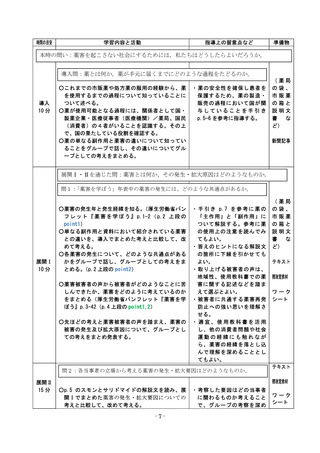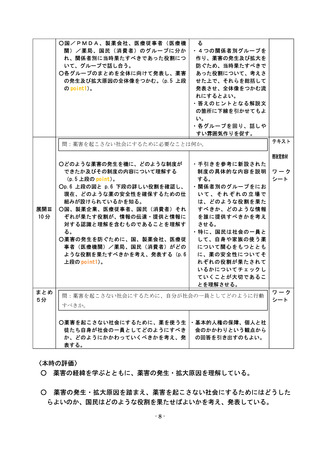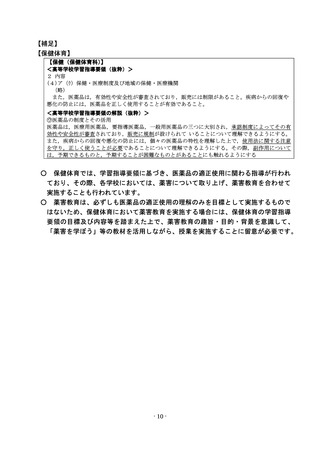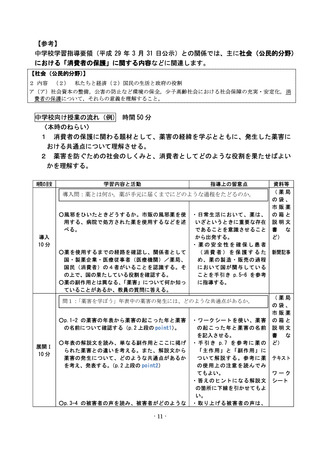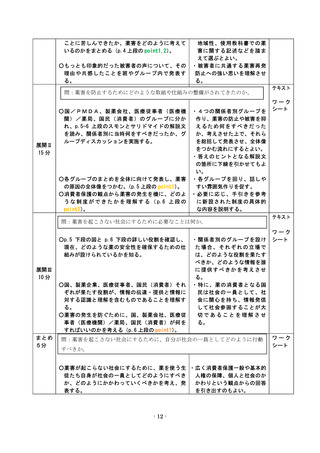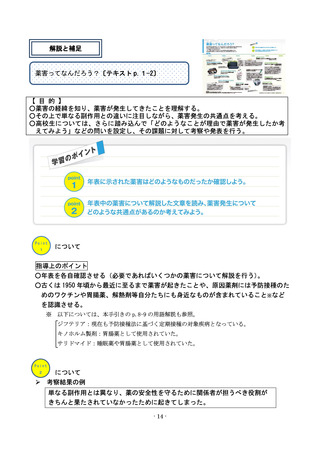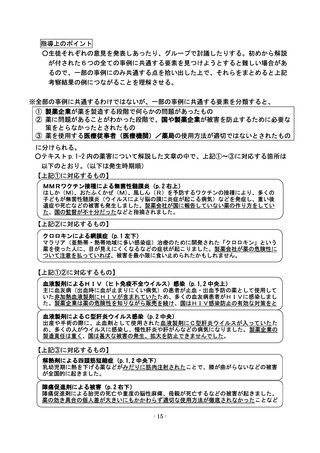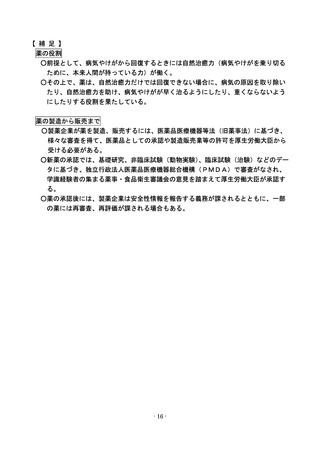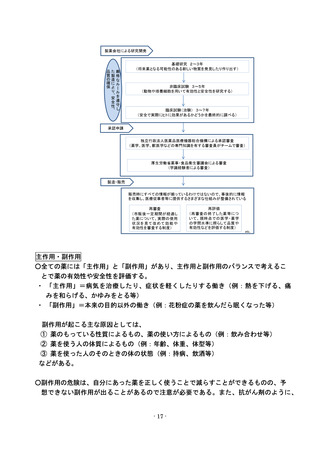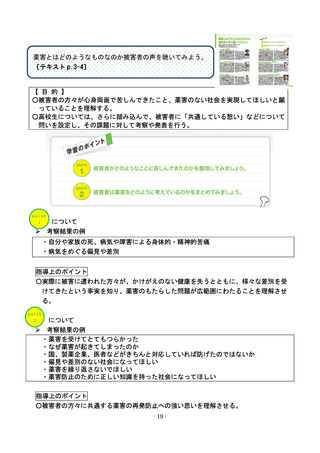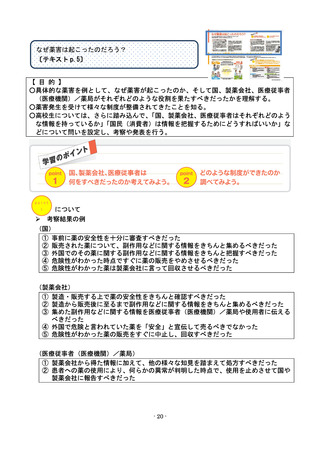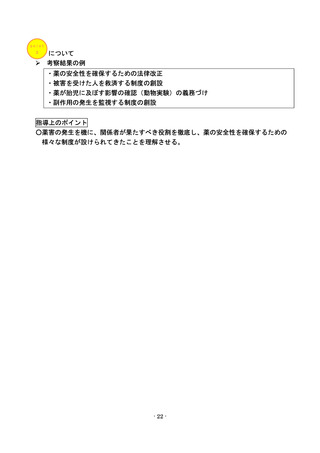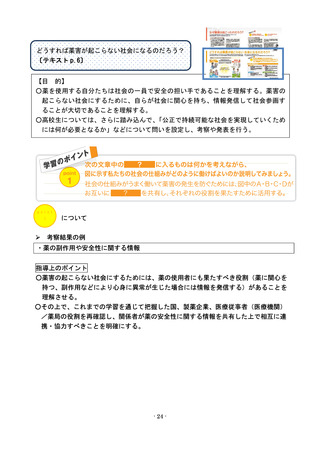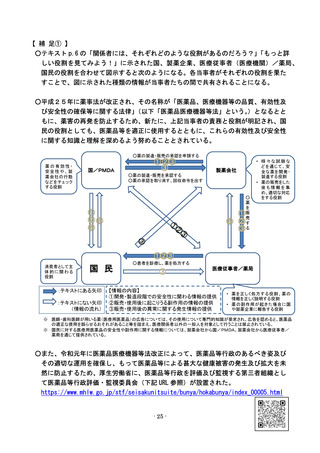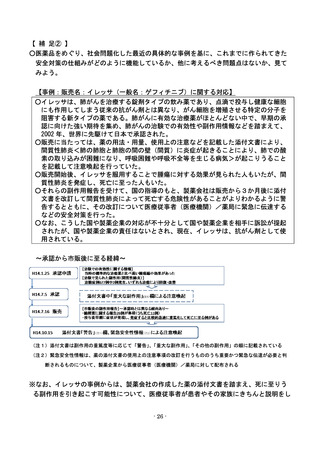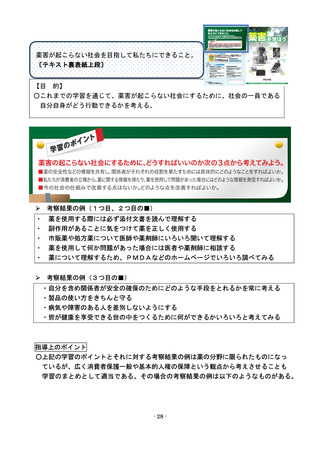よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 「薬害を学ぼう 指導の手引き(改訂版)」 (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000197733_00007.html |
| 出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬害を学び再発を防止するための教育に関する検討会(第23回 3/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
【参考】
中学校学習指導要領(平成 29 年 3 月 31 日公示)との関係では、主に社会(公民的分野)
における「消費者の保護」に関する内容などに関連します。
【社会(公民的分野)
】
2 内容 (2)
私たちと経済(2)国民の生活と政府の役割
ア(ア)社会資本の整備,公害の防止など環境の保全,少子高齢社会における社会保障の充実・安定化,消
費者の保護について,それらの意義を理解すること。
中学校向け授業の流れ(例) 時間 50 分
〈本時のねらい〉
1 消費者の保護に関わる題材として、薬害の経緯を学ぶとともに、発生した薬害に
おける共通点について理解させる。
2 薬害を防ぐための社会のしくみと、消費者としてどのような役割を果たせばよい
かを理解する。
時間の目安
学習内容と活動
指導上の留意点
○導入問:薬とは何か。薬が手元に届くまでにどのような過程をたどるのか。
○風邪をひいたときどうするか。市販の風邪薬を使
用する、病院で処方された薬を使用するなどを述
べる。
導入
10 分
○薬を使用するまでの経路を確認し、関係者として
国・製薬企業・医療従事者(医療機関)/薬局、
国民(消費者)の4者がいることを認識する。そ
の上で、国の果たしている役割を確認する。
○薬の副作用とは異なる、「薬害」について何か知っ
ていることがあるか、教員の質問に答える。
・日常生活において、薬は、
いざというときに重要な存在
であることを意識させること
から出発する。
・薬の安全性を確保し患者
(消費者)を保護するた
め、薬の製造・販売の過程
において国が関与している
ことを手引き p.5-6 を参考
に指導する。
問1:「薬害を学ぼう」年表中の薬害の発生には、どのような共通点があるか。
○p.1-2 の薬害の年表から薬害の起こった年と薬害
の名前について確認する(p.2 上段の point1)
。
展開Ⅰ
10 分
○年表の解説文を読み、単なる副作用とここに掲げ
られた薬害との違いを考える。また、解説文から
薬害の発生について、どのような共通点があるか
を考え、発表する。(p.2 上段の point2)
○p.3-4 の被害者の声を読み、被害者がどのような
- 11 -
・ワークシートを使い、薬害
の起こった年と薬害の名前
を記入させる。
・ 手 引 き p.7 を 参 考 に 薬 の
「主作用」と「副作用」に
ついて解説する。参考に薬
の使用上の注意を読んでみ
てもよい。
・答えのヒントになる解説文
の箇所に下線を引かせてもよ
い。
・取り上げる被害者の声は、
資料等
(薬局
の袋、
市販薬
の箱と
説明文
書 な
ど)
新聞記事
(薬局
の袋、
市販薬
の箱と
説明文
書 な
ど)
テキスト
ワーク
シート
中学校学習指導要領(平成 29 年 3 月 31 日公示)との関係では、主に社会(公民的分野)
における「消費者の保護」に関する内容などに関連します。
【社会(公民的分野)
】
2 内容 (2)
私たちと経済(2)国民の生活と政府の役割
ア(ア)社会資本の整備,公害の防止など環境の保全,少子高齢社会における社会保障の充実・安定化,消
費者の保護について,それらの意義を理解すること。
中学校向け授業の流れ(例) 時間 50 分
〈本時のねらい〉
1 消費者の保護に関わる題材として、薬害の経緯を学ぶとともに、発生した薬害に
おける共通点について理解させる。
2 薬害を防ぐための社会のしくみと、消費者としてどのような役割を果たせばよい
かを理解する。
時間の目安
学習内容と活動
指導上の留意点
○導入問:薬とは何か。薬が手元に届くまでにどのような過程をたどるのか。
○風邪をひいたときどうするか。市販の風邪薬を使
用する、病院で処方された薬を使用するなどを述
べる。
導入
10 分
○薬を使用するまでの経路を確認し、関係者として
国・製薬企業・医療従事者(医療機関)/薬局、
国民(消費者)の4者がいることを認識する。そ
の上で、国の果たしている役割を確認する。
○薬の副作用とは異なる、「薬害」について何か知っ
ていることがあるか、教員の質問に答える。
・日常生活において、薬は、
いざというときに重要な存在
であることを意識させること
から出発する。
・薬の安全性を確保し患者
(消費者)を保護するた
め、薬の製造・販売の過程
において国が関与している
ことを手引き p.5-6 を参考
に指導する。
問1:「薬害を学ぼう」年表中の薬害の発生には、どのような共通点があるか。
○p.1-2 の薬害の年表から薬害の起こった年と薬害
の名前について確認する(p.2 上段の point1)
。
展開Ⅰ
10 分
○年表の解説文を読み、単なる副作用とここに掲げ
られた薬害との違いを考える。また、解説文から
薬害の発生について、どのような共通点があるか
を考え、発表する。(p.2 上段の point2)
○p.3-4 の被害者の声を読み、被害者がどのような
- 11 -
・ワークシートを使い、薬害
の起こった年と薬害の名前
を記入させる。
・ 手 引 き p.7 を 参 考 に 薬 の
「主作用」と「副作用」に
ついて解説する。参考に薬
の使用上の注意を読んでみ
てもよい。
・答えのヒントになる解説文
の箇所に下線を引かせてもよ
い。
・取り上げる被害者の声は、
資料等
(薬局
の袋、
市販薬
の箱と
説明文
書 な
ど)
新聞記事
(薬局
の袋、
市販薬
の箱と
説明文
書 な
ど)
テキスト
ワーク
シート