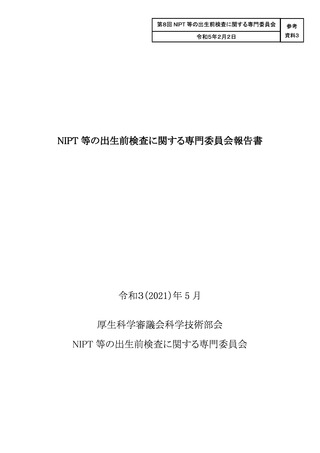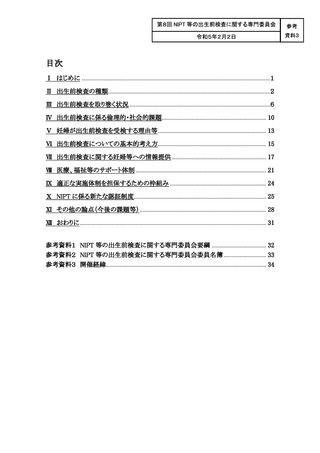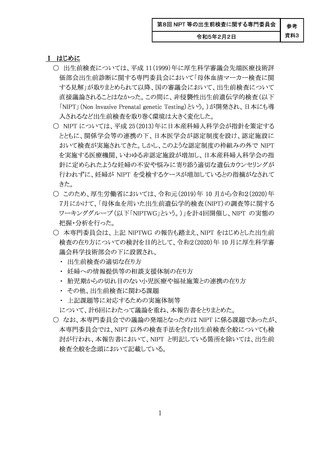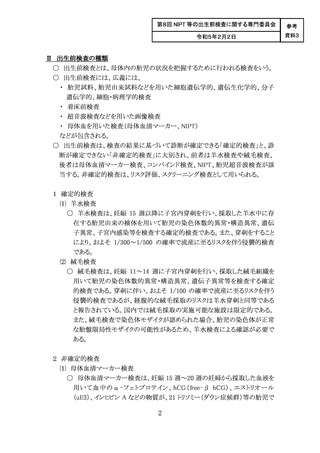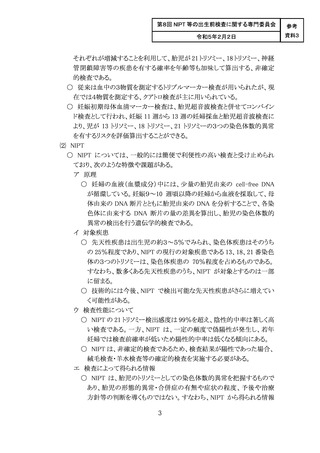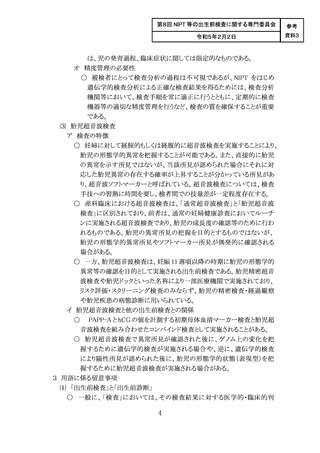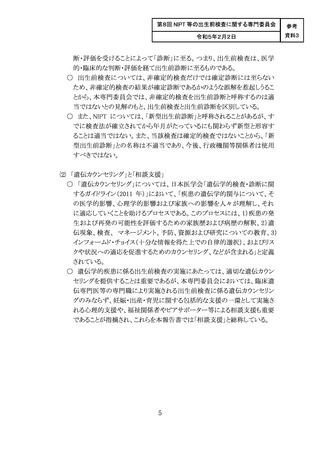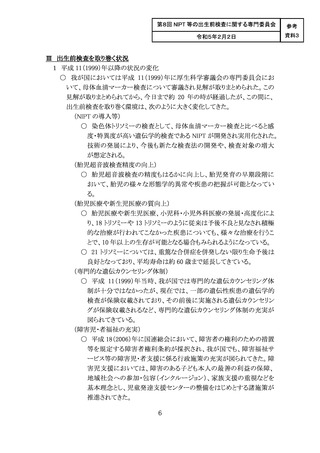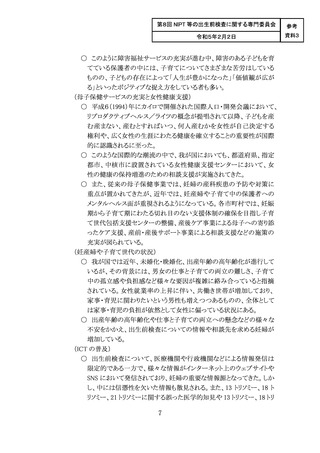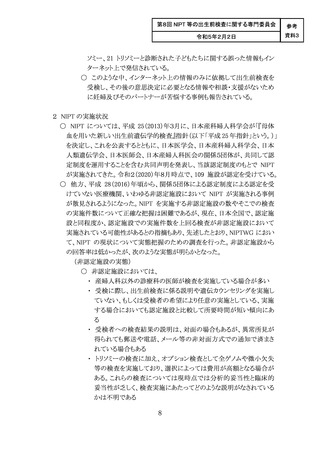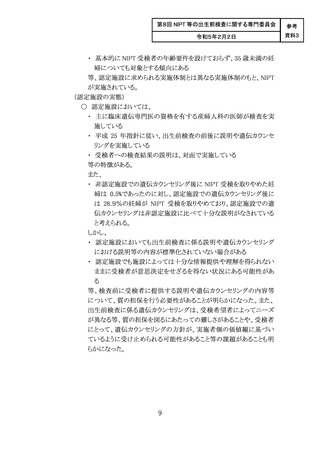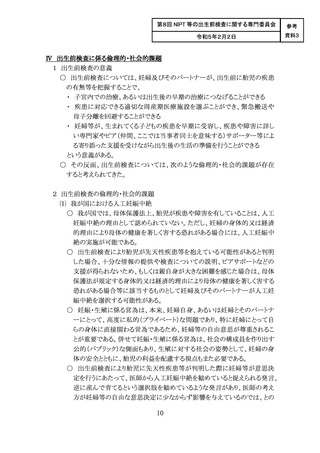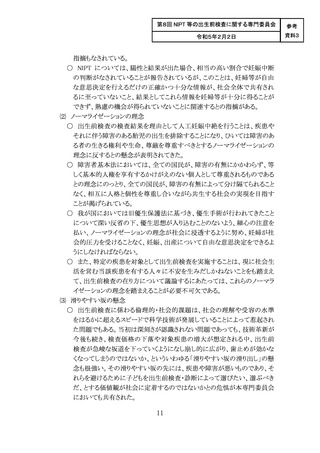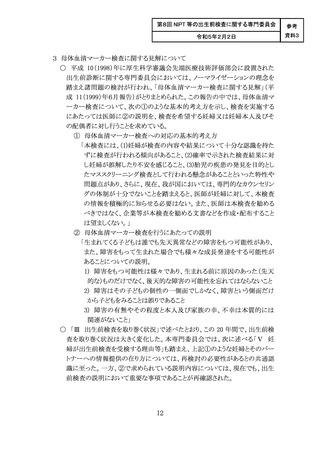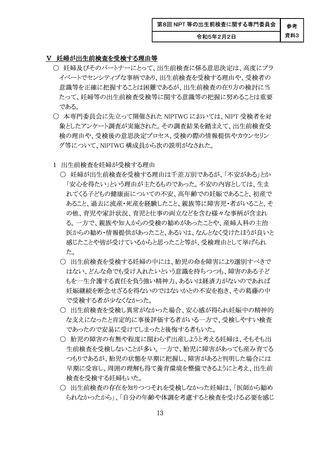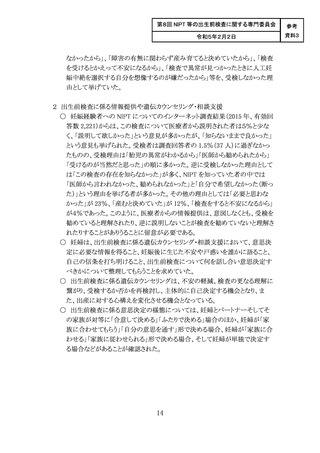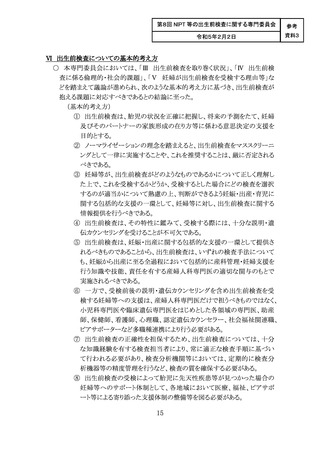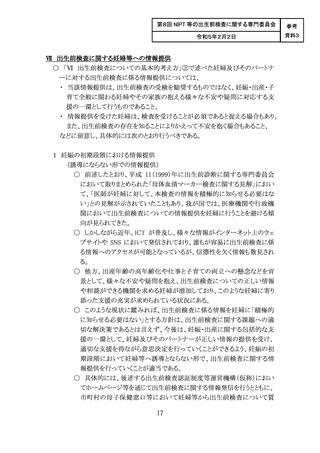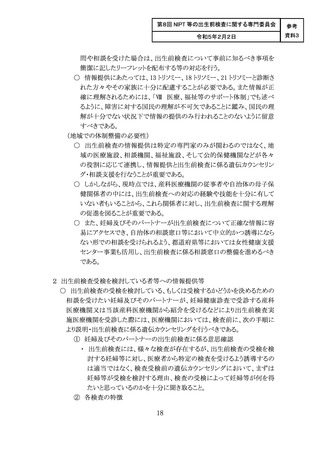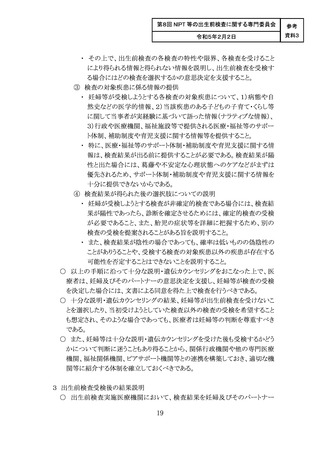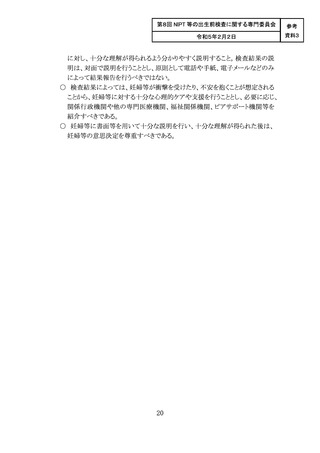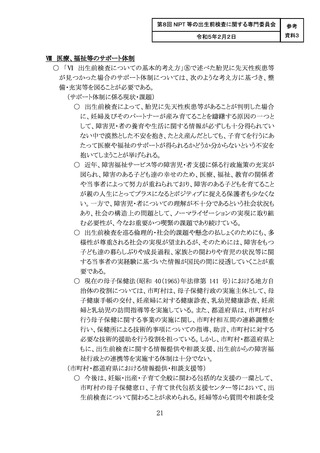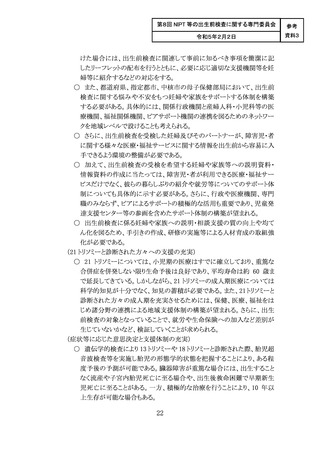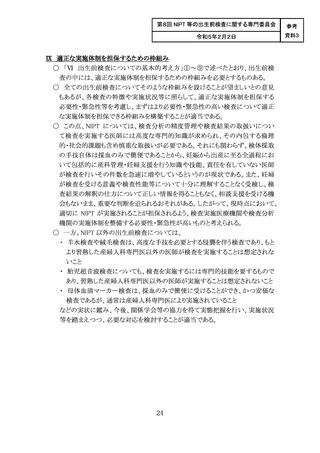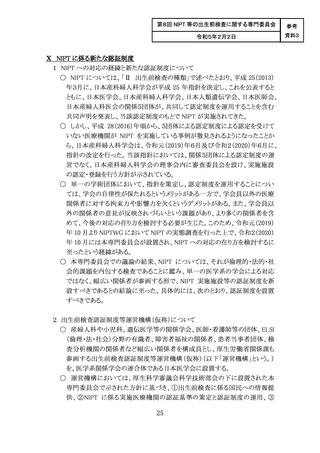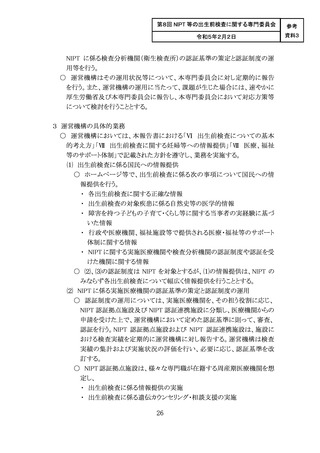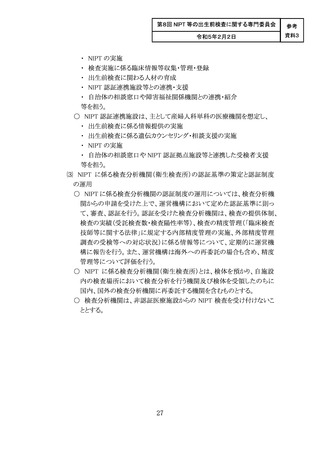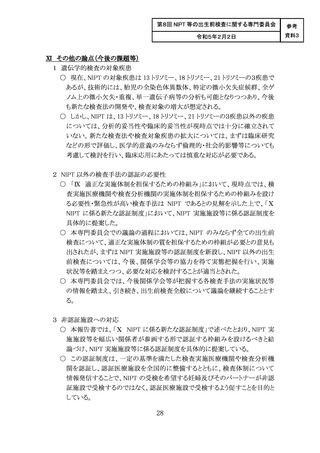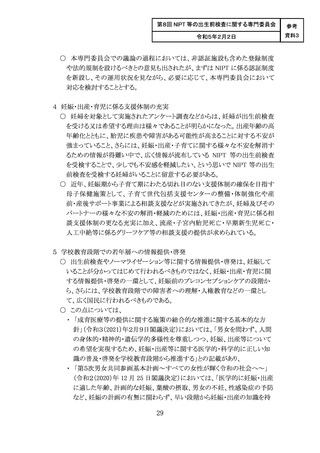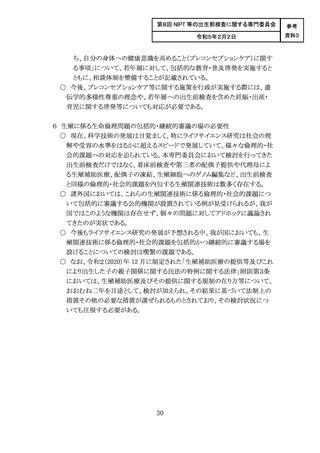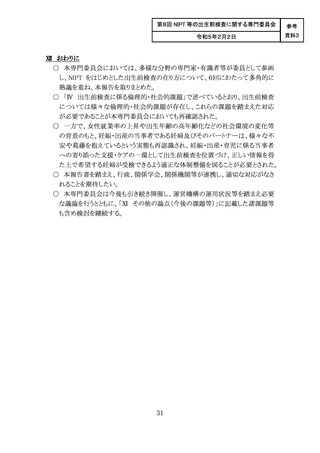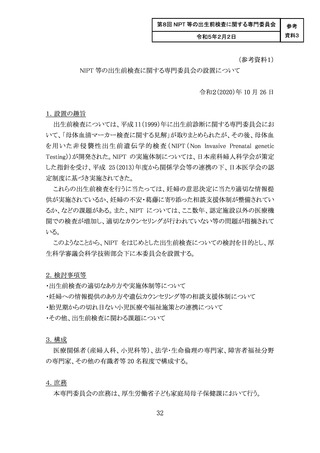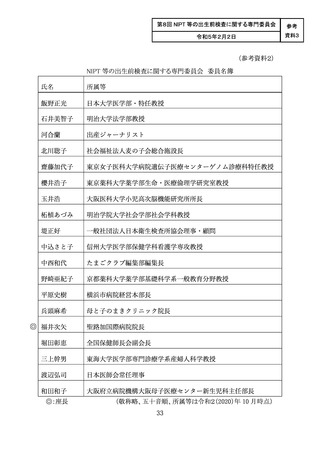よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 NIPT等の出生前検査に関する専門委員会報告書 (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30725.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会 NIPT等の出生前検査に関する専門委員会(第8回 2/2)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第8回 NIPT 等の出生前検査に関する専門委員会
参考
令和5年2月2日
資料3
Ⅶ 出生前検査に関する妊婦等への情報提供
○ 「Ⅵ 出生前検査についての基本的考え方」③で述べた妊婦及びそのパートナ
ーに対する出生前検査に係る情報提供については、
・ 当該情報提供は、出生前検査の受検を勧奨するものではなく、妊娠・出産・子
育て全般に関わる妊婦やその家族の抱える様々な不安や疑問に対応する支
援の一環として行うものであること、
・ 情報提供を受けた妊婦は、検査を受けることが必須であると捉える場合もあり、
また、出生前検査の存在を知ることによりかえって不安を抱く場合もあること、
などに留意し、具体的には次のとおり行うべきである。
1 妊娠の初期段階における情報提供
(誘導にならない形での情報提供)
〇 前述したとおり、平成 11(1999)年に出生前診断に関する専門委員会
において取りまとめられた「母体血清マーカー検査に関する見解」におい
て、「医師が妊婦に対して、本検査の情報を積極的に知らせる必要はな
い」との見解が示されていたこともあり、我が国では、医療機関や行政機
関において出生前検査についての情報提供を妊婦に行うことを避ける傾
向が見られてきた。
〇 しかしながら近年、ICT が普及し、様々な情報がインターネット上のウェ
ブサイトや SNS において発信されており、誰もが容易に出生前検査に係
る情報へのアクセスが可能となっているが、信憑性を欠く情報も散見され
る。
〇 他方、出産年齢の高年齢化や仕事と子育ての両立への懸念などを背
景として、様々な不安や疑問を抱え、出生前検査についての正しい情報
や相談ができる機関を求める妊婦が増加しており、このような妊婦に寄り
添った支援の充実が求められている状況にある。
〇 このような現状に鑑みれば、出生前検査に係る情報を妊婦に「積極的
に知らせる必要はない」とする方針は、出生前検査に関する課題への適
切な解決策であるとは言えず、今後は、妊娠・出産に関する包括的な支
援の一環として、妊婦及びそのパートナーが正しい情報の提供を受け、
適切な支援を得ながら意思決定を行っていくことができるよう、妊娠の初
期段階において妊婦等へ誘導とならない形で、出生前検査に関する情
報提供を行っていくことが適当である。
〇 具体的には、後述する出生前検査認証制度等運営機構(仮称)におい
てホームページ等を通じて出生前検査に関する情報発信を行うとともに、
市町村の母子保健窓口等において妊婦等から出生前検査について質
17
参考
令和5年2月2日
資料3
Ⅶ 出生前検査に関する妊婦等への情報提供
○ 「Ⅵ 出生前検査についての基本的考え方」③で述べた妊婦及びそのパートナ
ーに対する出生前検査に係る情報提供については、
・ 当該情報提供は、出生前検査の受検を勧奨するものではなく、妊娠・出産・子
育て全般に関わる妊婦やその家族の抱える様々な不安や疑問に対応する支
援の一環として行うものであること、
・ 情報提供を受けた妊婦は、検査を受けることが必須であると捉える場合もあり、
また、出生前検査の存在を知ることによりかえって不安を抱く場合もあること、
などに留意し、具体的には次のとおり行うべきである。
1 妊娠の初期段階における情報提供
(誘導にならない形での情報提供)
〇 前述したとおり、平成 11(1999)年に出生前診断に関する専門委員会
において取りまとめられた「母体血清マーカー検査に関する見解」におい
て、「医師が妊婦に対して、本検査の情報を積極的に知らせる必要はな
い」との見解が示されていたこともあり、我が国では、医療機関や行政機
関において出生前検査についての情報提供を妊婦に行うことを避ける傾
向が見られてきた。
〇 しかしながら近年、ICT が普及し、様々な情報がインターネット上のウェ
ブサイトや SNS において発信されており、誰もが容易に出生前検査に係
る情報へのアクセスが可能となっているが、信憑性を欠く情報も散見され
る。
〇 他方、出産年齢の高年齢化や仕事と子育ての両立への懸念などを背
景として、様々な不安や疑問を抱え、出生前検査についての正しい情報
や相談ができる機関を求める妊婦が増加しており、このような妊婦に寄り
添った支援の充実が求められている状況にある。
〇 このような現状に鑑みれば、出生前検査に係る情報を妊婦に「積極的
に知らせる必要はない」とする方針は、出生前検査に関する課題への適
切な解決策であるとは言えず、今後は、妊娠・出産に関する包括的な支
援の一環として、妊婦及びそのパートナーが正しい情報の提供を受け、
適切な支援を得ながら意思決定を行っていくことができるよう、妊娠の初
期段階において妊婦等へ誘導とならない形で、出生前検査に関する情
報提供を行っていくことが適当である。
〇 具体的には、後述する出生前検査認証制度等運営機構(仮称)におい
てホームページ等を通じて出生前検査に関する情報発信を行うとともに、
市町村の母子保健窓口等において妊婦等から出生前検査について質
17