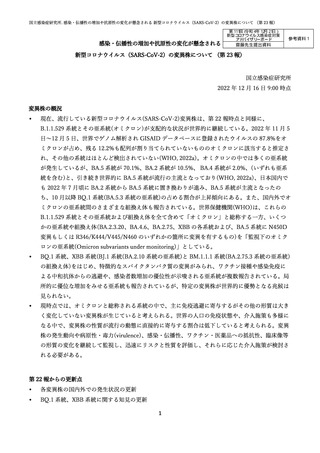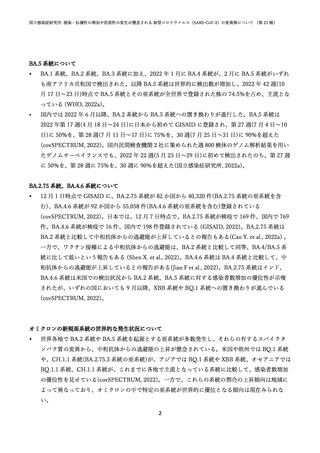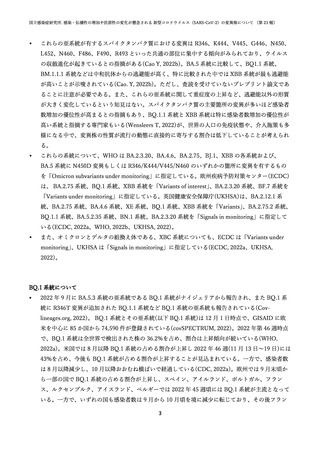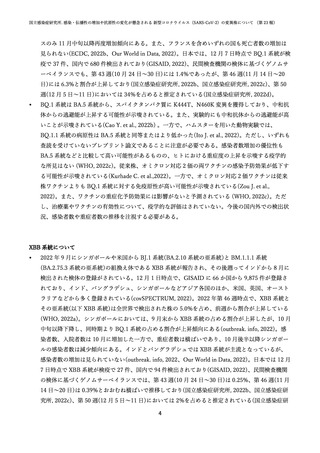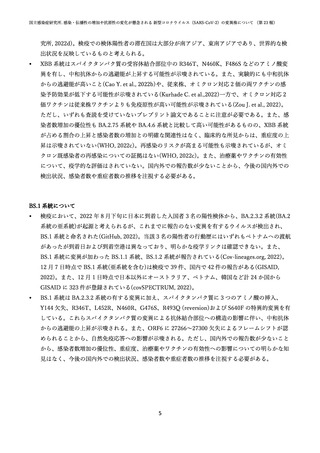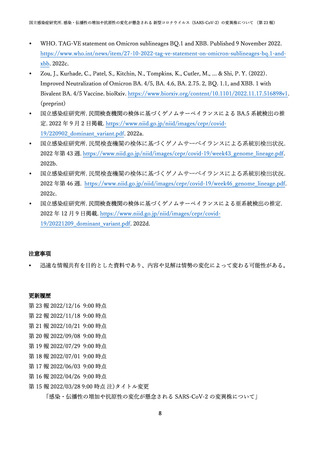よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 変異株リスク評価 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html |
| 出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード (第111回 12/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
国立感染症研究所. 感染・伝播性の増加や抗原性の変化が懸念される 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の変異株について (第 23 報)
感染・伝播性の増加や抗原性の変化が懸念される
第111回(令和4年12月21日)
新型コロナウイルス感染症対策
アドバイザリーボード
参考資料1
齋藤先生提出資料
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の変異株について (第 23 報)
国立感染症研究所
2022 年 12 月 16 日 9:00 時点
変異株の概況
現在、流行している新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)変異株は、第 22 報時点と同様に、
B.1.1.529 系統とその亜系統(オミクロン)が支配的な状況が世界的に継続している。2022 年 11 月 5
日~12 月 5 日、世界でゲノム解析され GISAID データベースに登録されたウイルスの 87.8%をオ
ミクロンが占め、残る 12.2%も配列が割り当てられていないもののオミクロンに該当すると推定さ
れ、その他の系統はほとんど検出されていない(WHO, 2022a)。オミクロンの中では多くの亜系統
が発生しているが、BA.5 系統が 70.1%、BA.2 系統が 10.5%、 BA.4 系統が 2.0%、(いずれも亜系
統を含む)と、引き続き世界的に BA.5 系統が流行の主流となっており(WHO, 2022a)、日本国内で
も 2022 年 7 月頃に BA.2 系統から BA.5 系統に置き換わりが進み、BA.5 系統が主流となったの
ち、10 月以降 BQ.1 系統(BA.5.3 系統の亜系統)の占める割合が上昇傾向にある。また、国内外でオ
ミクロンの亜系統間のさまざまな組換え体も報告されている。世界保健機関(WHO)は、これらの
B.1.1.529 系統とその亜系統および組換え体を全て含めて「オミクロン」と総称する一方、いくつ
かの亜系統や組換え体(BA.2.3.20、BA.4.6、BA.2.75、XBB の各系統および、BA.5 系統に N450D
変異もしくは R346/K444/V445/N460 のいずれかの箇所に変異を有するもの)を「監視下のオミク
ロンの亜系統(Omicron subvariants under monitoring)」としている。
BQ.1 系統、XBB 系統(BJ.1 系統(BA.2.10 系統の亜系統)と BM.1.1.1 系統(BA.2.75.3 系統の亜系統)
の組換え体)をはじめ、特徴的なスパイクタンパク質の変異がみられ、ワクチン接種や感染免疫に
よる中和抗体からの逃避や、感染者数増加の優位性が示唆される亜系統が複数報告されている。局
所的に優位な増加をみせる亜系統も報告されているが、特定の変異株が世界的に優勢となる兆候は
見られない。
現時点では、オミクロンと総称される系統の中で、主に免疫逃避に寄与するがその他の形質は大き
く変化していない変異株が生じていると考えられる。世界の人口の免疫状態や、介入施策も多様に
なる中で、変異株の性質が流行の動態に直接的に寄与する割合は低下していると考えられる。変異
株の発生動向や病原性・毒力(virulence)、感染・伝播性、ワクチン・医薬品への抵抗性、臨床像等
の形質の変化を継続して監視し、迅速にリスクと性質を評価し、それらに応じた介入施策が検討さ
れる必要がある。
第 22 報からの更新点
各変異株の国内外での発生状況の更新
BQ.1 系統、XBB 系統に関する知見の更新
1
感染・伝播性の増加や抗原性の変化が懸念される
第111回(令和4年12月21日)
新型コロナウイルス感染症対策
アドバイザリーボード
参考資料1
齋藤先生提出資料
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の変異株について (第 23 報)
国立感染症研究所
2022 年 12 月 16 日 9:00 時点
変異株の概況
現在、流行している新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)変異株は、第 22 報時点と同様に、
B.1.1.529 系統とその亜系統(オミクロン)が支配的な状況が世界的に継続している。2022 年 11 月 5
日~12 月 5 日、世界でゲノム解析され GISAID データベースに登録されたウイルスの 87.8%をオ
ミクロンが占め、残る 12.2%も配列が割り当てられていないもののオミクロンに該当すると推定さ
れ、その他の系統はほとんど検出されていない(WHO, 2022a)。オミクロンの中では多くの亜系統
が発生しているが、BA.5 系統が 70.1%、BA.2 系統が 10.5%、 BA.4 系統が 2.0%、(いずれも亜系
統を含む)と、引き続き世界的に BA.5 系統が流行の主流となっており(WHO, 2022a)、日本国内で
も 2022 年 7 月頃に BA.2 系統から BA.5 系統に置き換わりが進み、BA.5 系統が主流となったの
ち、10 月以降 BQ.1 系統(BA.5.3 系統の亜系統)の占める割合が上昇傾向にある。また、国内外でオ
ミクロンの亜系統間のさまざまな組換え体も報告されている。世界保健機関(WHO)は、これらの
B.1.1.529 系統とその亜系統および組換え体を全て含めて「オミクロン」と総称する一方、いくつ
かの亜系統や組換え体(BA.2.3.20、BA.4.6、BA.2.75、XBB の各系統および、BA.5 系統に N450D
変異もしくは R346/K444/V445/N460 のいずれかの箇所に変異を有するもの)を「監視下のオミク
ロンの亜系統(Omicron subvariants under monitoring)」としている。
BQ.1 系統、XBB 系統(BJ.1 系統(BA.2.10 系統の亜系統)と BM.1.1.1 系統(BA.2.75.3 系統の亜系統)
の組換え体)をはじめ、特徴的なスパイクタンパク質の変異がみられ、ワクチン接種や感染免疫に
よる中和抗体からの逃避や、感染者数増加の優位性が示唆される亜系統が複数報告されている。局
所的に優位な増加をみせる亜系統も報告されているが、特定の変異株が世界的に優勢となる兆候は
見られない。
現時点では、オミクロンと総称される系統の中で、主に免疫逃避に寄与するがその他の形質は大き
く変化していない変異株が生じていると考えられる。世界の人口の免疫状態や、介入施策も多様に
なる中で、変異株の性質が流行の動態に直接的に寄与する割合は低下していると考えられる。変異
株の発生動向や病原性・毒力(virulence)、感染・伝播性、ワクチン・医薬品への抵抗性、臨床像等
の形質の変化を継続して監視し、迅速にリスクと性質を評価し、それらに応じた介入施策が検討さ
れる必要がある。
第 22 報からの更新点
各変異株の国内外での発生状況の更新
BQ.1 系統、XBB 系統に関する知見の更新
1