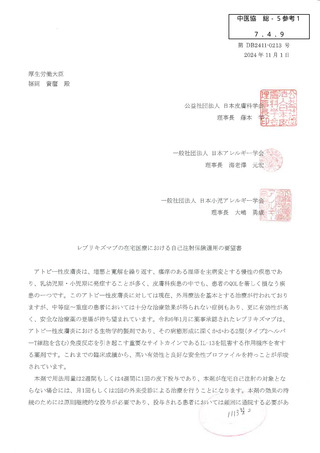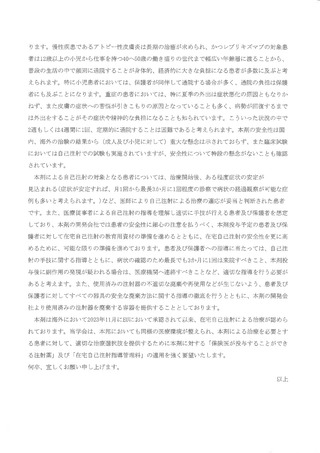よむ、つかう、まなぶ。
総-5参考1 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56712.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第606回 4/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ります。 慢性疾患であるアトピー性友膚炎は長期の治癒が求められ、かつレブリキズマブの対象吊
者は12蔵以上の小児から仕事を持つ40へ50歳の働き盛りの世代まで幅広い年齢層に渡ることから、
普段の生活の中で疾回に通院することが身体的、経済的に大きな負担になる愚者が多数に及ぶと考
えられます。 特に小児患者においては、保護者が同伴して通院する場合が多く、通院の負担は保護
者にも及記ことになります。 重症の吊者においては、特に夏季の外出は症状悪化の原因ともなりか
ねず、また友膚の症状への苦悩が引きこもりの原因となっていることも多く、病勢が回復するまで
は外出をすることがその症状や精神的な負担になることも知られています。こういった状況の中で
2週もしくは4週間に1回、定期的に通院することは困難であると考えられます。本剤の安全性は国
内、海外の治験の結果から (成人及び小児に対して) 重大な懸念は示されておらず、また臨床試験
においては目己注射での試験も実施きれていますが、安全性について特段の懸念がないことも確認
されています。
本剤による自己注射の対象となる愚者については、治療開始後、ある程度症状の安定が
見込まれる(症状が安定すれば、月1回から最長3か月に1回程度の診察で病状の経過観察が可能な症
例も多いと考えられます。)など、医師により自己注射による治療の適床が妥当と判断された吊者
です。また、医療従事者による自己注射の指導を理解 し適切に手技が行える患者及び保護者を想定
しており、本剤の開発会社では患者の安全性に細心の注意を払うべく、本剤投与予定の患者及び保
護者に対して在宅目己注射の教育用資材の準備を進めるとともに、在宅自己注射の安全性を更に高
めるために、可能な限りの準備を進めております。 愚者及び保護者への凍導に当たっては、自己注
射の手技に関する指導とともに、病状の確認のため最長でも3か月に1回は来院すべきこと、本剤投
与後に副作用の発現が疑われる場合は、医療機関へ連絡すべきことなど、適切な指導を行う必要が
あると考えます。また、使用済みの注射器の不適切な廃棄や再使用などが生じないよう、軸者及び
保護者に対してすべての器具の安全な廃棄方法に関する指導の徹底を行うとともに、本剤の開発会
社より使用済みの注射器を廃棄する容器を提供することとしております。
本剤は海外において2023年11月にEUにおいて承認されて以来、在宅自己注射による治療が認めら
れております。当学会は、本邦においても同様の医療環境が整えられ、本剤による治療を必要とす
る愚者に対して、適切な治療選択肢を提供するために本剤に対する 「保険医が投与することができ
る注射薬」及び「在宅自己注射指導管理料」 の適用を強く要望いたします。
何卒、宮しくお願い申 し上げます。
以上
者は12蔵以上の小児から仕事を持つ40へ50歳の働き盛りの世代まで幅広い年齢層に渡ることから、
普段の生活の中で疾回に通院することが身体的、経済的に大きな負担になる愚者が多数に及ぶと考
えられます。 特に小児患者においては、保護者が同伴して通院する場合が多く、通院の負担は保護
者にも及記ことになります。 重症の吊者においては、特に夏季の外出は症状悪化の原因ともなりか
ねず、また友膚の症状への苦悩が引きこもりの原因となっていることも多く、病勢が回復するまで
は外出をすることがその症状や精神的な負担になることも知られています。こういった状況の中で
2週もしくは4週間に1回、定期的に通院することは困難であると考えられます。本剤の安全性は国
内、海外の治験の結果から (成人及び小児に対して) 重大な懸念は示されておらず、また臨床試験
においては目己注射での試験も実施きれていますが、安全性について特段の懸念がないことも確認
されています。
本剤による自己注射の対象となる愚者については、治療開始後、ある程度症状の安定が
見込まれる(症状が安定すれば、月1回から最長3か月に1回程度の診察で病状の経過観察が可能な症
例も多いと考えられます。)など、医師により自己注射による治療の適床が妥当と判断された吊者
です。また、医療従事者による自己注射の指導を理解 し適切に手技が行える患者及び保護者を想定
しており、本剤の開発会社では患者の安全性に細心の注意を払うべく、本剤投与予定の患者及び保
護者に対して在宅目己注射の教育用資材の準備を進めるとともに、在宅自己注射の安全性を更に高
めるために、可能な限りの準備を進めております。 愚者及び保護者への凍導に当たっては、自己注
射の手技に関する指導とともに、病状の確認のため最長でも3か月に1回は来院すべきこと、本剤投
与後に副作用の発現が疑われる場合は、医療機関へ連絡すべきことなど、適切な指導を行う必要が
あると考えます。また、使用済みの注射器の不適切な廃棄や再使用などが生じないよう、軸者及び
保護者に対してすべての器具の安全な廃棄方法に関する指導の徹底を行うとともに、本剤の開発会
社より使用済みの注射器を廃棄する容器を提供することとしております。
本剤は海外において2023年11月にEUにおいて承認されて以来、在宅自己注射による治療が認めら
れております。当学会は、本邦においても同様の医療環境が整えられ、本剤による治療を必要とす
る愚者に対して、適切な治療選択肢を提供するために本剤に対する 「保険医が投与することができ
る注射薬」及び「在宅自己注射指導管理料」 の適用を強く要望いたします。
何卒、宮しくお願い申 し上げます。
以上