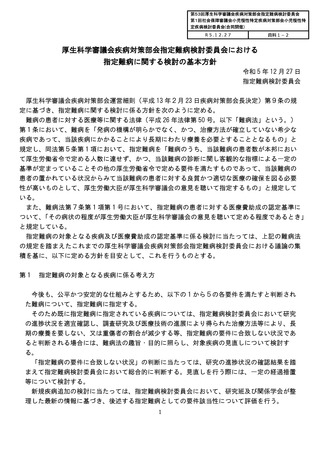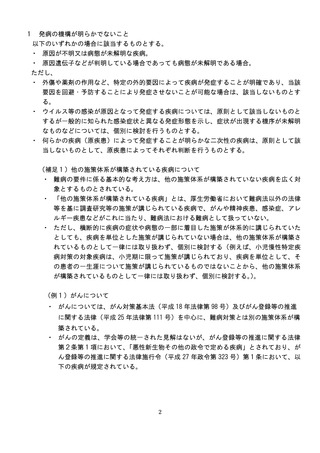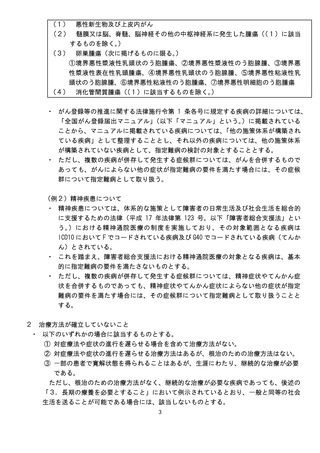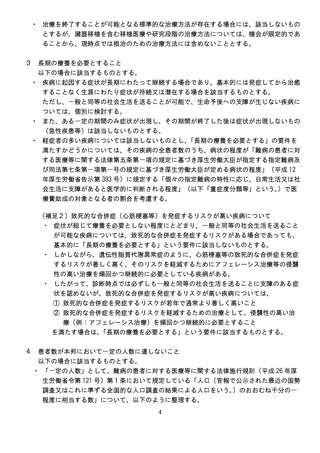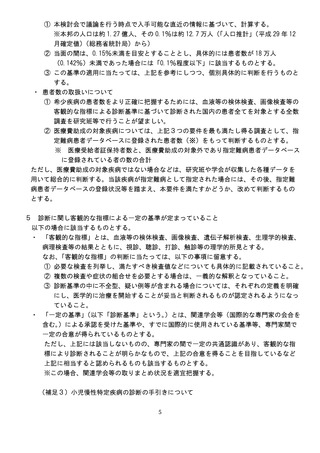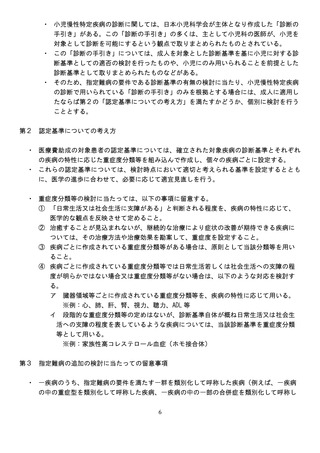よむ、つかう、まなぶ。
資料1-2 厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会における指定難病に関する検討の基本方針 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37155.html |
| 出典情報 | 第53回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会、第1回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(合同開催)(12/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
① 本検討会で議論を行う時点で入手可能な直近の情報に基づいて、計算する。
※本邦の人口は約 1.27 億人、その 0.1%は約 12.7 万人(「人口推計」(平成 29 年 12
月確定値)(総務省統計局)から)
② 当面の間は、0.15%未満を目安とすることとし、具体的には患者数が 18 万人
(0.142%)未満であった場合には「0.1%程度以下」に該当するものとする。
③ この基準の適用に当たっては、上記を参考にしつつ、個別具体的に判断を行うものと
する。
・ 患者数の取扱いについて
① 希少疾病の患者数をより正確に把握するためには、血液等の検体検査、画像検査等の
客観的な指標による診断基準に基づいて診断された国内の患者全てを対象とする全数
調査を研究班等で行うことが望ましい。
② 医療費助成の対象疾病については、上記3つの要件を最も満たし得る調査として、指
定難病患者データベースに登録された患者数(※)をもって判断するものとする。
※
医療受給者証保持者数と、医療費助成の対象外であり指定難病患者データベース
に登録されている者の数の合計
ただし、医療費助成の対象疾病ではない場合などは、研究班や学会が収集した各種データを
用いて総合的に判断する。当該疾病が指定難病として指定された場合には、その後、指定難
病患者データベースの登録状況等を踏まえ、本要件を満たすかどうか、改めて判断するもの
とする。
5
診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていること
以下の場合に該当するものとする。
・ 「客観的な指標」とは、血液等の検体検査、画像検査、遺伝子解析検査、生理学的検査、
病理検査等の結果とともに、視診、聴診、打診、触診等の理学的所見とする。
なお、「客観的な指標」の判断に当たっては、以下の事項に留意する。
① 必要な検査を列挙し、満たすべき検査値などについても具体的に記載されていること。
② 複数の検査や症状の組合せを必要とする場合は、一義的な解釈となっていること。
③ 診断基準の中に不全型、疑い例等が含まれる場合については、それぞれの定義を明確
にし、医学的に治療を開始することが妥当と判断されるものが認定されるようになっ
ていること。
・ 「一定の基準」
(以下「診断基準」という。)とは、関連学会等(国際的な専門家の会合を
含む。)による承認を受けた基準や、すでに国際的に使用されている基準等、専門家間で
一定の合意が得られているものとする。
ただし、上記には該当しないものの、専門家の間で一定の共通認識があり、客観的な指
標により診断されることが明らかなもので、上記の合意を得ることを目指しているなど
上記に相当すると認められるものも該当するものとする。
※この場合、関連学会等の取りまとめ状況を適宜把握する。
(補足3)小児慢性特定疾病の診断の手引きについて
5
※本邦の人口は約 1.27 億人、その 0.1%は約 12.7 万人(「人口推計」(平成 29 年 12
月確定値)(総務省統計局)から)
② 当面の間は、0.15%未満を目安とすることとし、具体的には患者数が 18 万人
(0.142%)未満であった場合には「0.1%程度以下」に該当するものとする。
③ この基準の適用に当たっては、上記を参考にしつつ、個別具体的に判断を行うものと
する。
・ 患者数の取扱いについて
① 希少疾病の患者数をより正確に把握するためには、血液等の検体検査、画像検査等の
客観的な指標による診断基準に基づいて診断された国内の患者全てを対象とする全数
調査を研究班等で行うことが望ましい。
② 医療費助成の対象疾病については、上記3つの要件を最も満たし得る調査として、指
定難病患者データベースに登録された患者数(※)をもって判断するものとする。
※
医療受給者証保持者数と、医療費助成の対象外であり指定難病患者データベース
に登録されている者の数の合計
ただし、医療費助成の対象疾病ではない場合などは、研究班や学会が収集した各種データを
用いて総合的に判断する。当該疾病が指定難病として指定された場合には、その後、指定難
病患者データベースの登録状況等を踏まえ、本要件を満たすかどうか、改めて判断するもの
とする。
5
診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていること
以下の場合に該当するものとする。
・ 「客観的な指標」とは、血液等の検体検査、画像検査、遺伝子解析検査、生理学的検査、
病理検査等の結果とともに、視診、聴診、打診、触診等の理学的所見とする。
なお、「客観的な指標」の判断に当たっては、以下の事項に留意する。
① 必要な検査を列挙し、満たすべき検査値などについても具体的に記載されていること。
② 複数の検査や症状の組合せを必要とする場合は、一義的な解釈となっていること。
③ 診断基準の中に不全型、疑い例等が含まれる場合については、それぞれの定義を明確
にし、医学的に治療を開始することが妥当と判断されるものが認定されるようになっ
ていること。
・ 「一定の基準」
(以下「診断基準」という。)とは、関連学会等(国際的な専門家の会合を
含む。)による承認を受けた基準や、すでに国際的に使用されている基準等、専門家間で
一定の合意が得られているものとする。
ただし、上記には該当しないものの、専門家の間で一定の共通認識があり、客観的な指
標により診断されることが明らかなもので、上記の合意を得ることを目指しているなど
上記に相当すると認められるものも該当するものとする。
※この場合、関連学会等の取りまとめ状況を適宜把握する。
(補足3)小児慢性特定疾病の診断の手引きについて
5